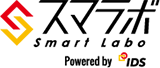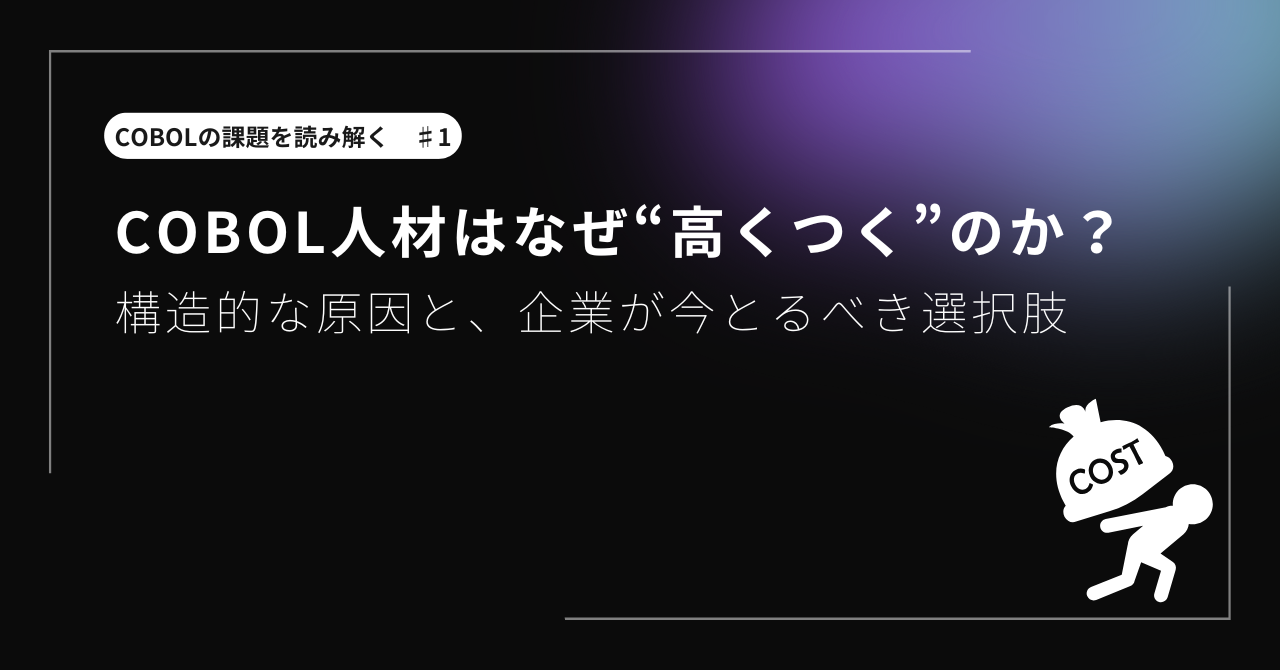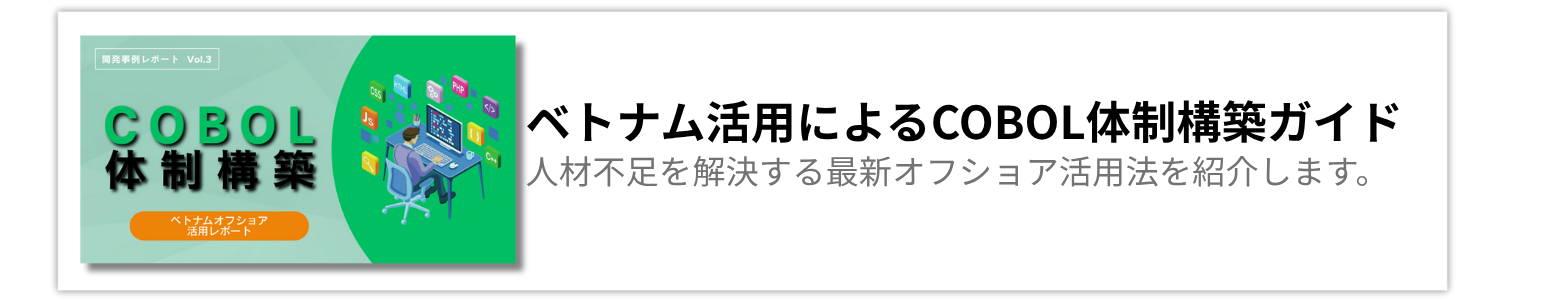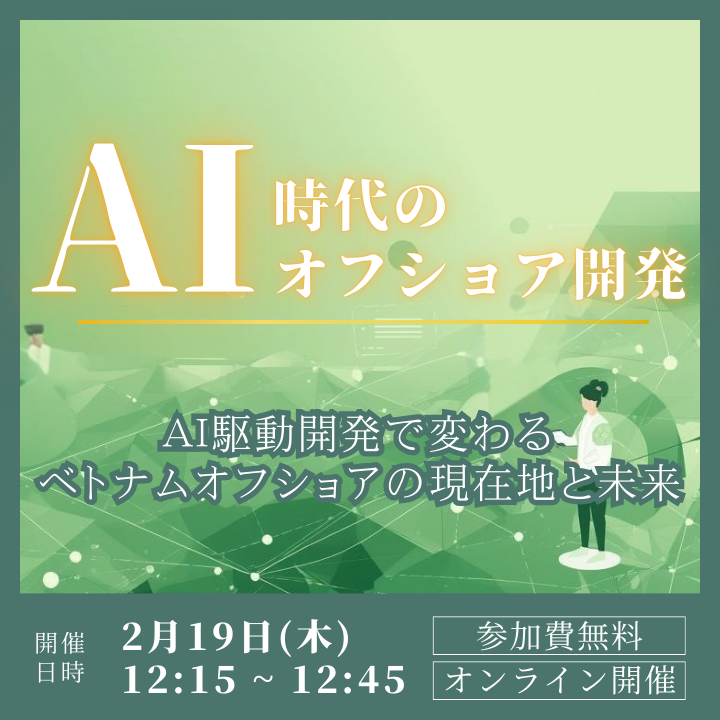こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
「COBOL人材が足りない」——この言葉は、IT業界や自治体、金融機関などの現場ではもはや常識となりつつあります。その中でも、より深刻化しているのがCOBOL人材の人件費高騰という現実です。
開発・保守を外部に委託しようとした企業が、予算の壁に直面してプロジェクトを断念するケースも珍しくありません。
本記事では、COBOL人材の人件費がなぜ高騰しているのか、どの程度高騰しているのか、企業はどう対処しているのか、そして今後の現実的な解決策はどこにあるのかについて、データと現場の実態をもとに解説していきます。
この記事はこんな人にオススメ!
COBOL人材の確保が難しく、業務が属人化していると感じている
外注コストが年々上昇し、継続的な委託体制に限界を感じている
中長期的なCOBOL運用体制の見直しを検討している
目次
需要に対して供給が足りない──COBOL技術者市場のいびつな構造
COBOL技術者の需給バランスは、他のITスキルと比べても極端に崩れています。
背景には、COBOLがかつてメインフレーム中心のシステム開発で主流だった時代からの時間的経過があります。
1970〜90年代に構築された基幹システムの多くがCOBOLで動いている一方で、COBOLを新たに学ぶ人がほとんどいないため、人材の供給が完全に途絶えている状態なのです。
それでも、銀行・生保・官公庁・物流・製造業など、COBOLで動くシステムは今も数多く現役です。
つまり、「メンテナンスが必要なシステムは存在するのに、それを扱える人がいない」という極端な人材市場が形成されており、
これがCOBOL人材の高単価化を招く大きな要因となっています。
実際にどれくらい高いのか?単価例とその現実
では、実際にCOBOL技術者の人件費はどの程度なのでしょうか。
調査データによれば、COBOLエンジニアの平均年収は約700万円前後、時給にして3,300円台が一般的な水準とされています。この数字だけを見ると、他のエンジニアと大きく変わらないようにも思えます。
しかし、実務においてはこの“平均値”があまり参考にならないケースも少なくありません。たとえば、フリーランス契約やSESなどの外注案件では、月単価90万〜130万円前後で取引されることが多く、COBOL経験10年以上のシニア人材では、時給換算で5,000〜7,000円に達することもあります。
これはあくまで“運用保守レベル”の金額であり、要件定義・ドキュメント整備・マイグレーション検討など、より上流の業務が伴う場合は月150万円を超える見積もりが提示されるケースも珍しくありません。
一方で、「社内にCOBOL人材がいないため、急場しのぎでJavaやPythonエンジニアに短期教育してアサインした」という企業の声もあります。しかしその多くは、品質・再現性・継続性の面で課題が大きく、結果的に“失敗プロジェクト”になったという報告も見られます。
つまり、COBOL案件の単価が高騰している背景には、単なる希少価値だけでなく、業務の属人性や専門性の高さ、再現性の低さがコストを押し上げる構造が存在しているのです。
なぜ高単価化するのか?3つの要因
では、こうした高騰がなぜ起きているのか。その要因は大きく3つに整理できます。
1. 退職・引退による残存人材の“プレミア化”
技術力は高くても、すでに60代・70代というCOBOL技術者が多くを占めています。この世代が順次退職していく中で、残された少数の経験者が極めて希少な人材として高額で取引される構図が生まれています。
企業によっては「元社員を再雇用」「退職OBに週3で来てもらう」などの対応を取っているものの、それでも人材が間に合わず、外注単価が上昇せざるを得ない状況です。
2. 属人化されたシステムに“経験値プレミアム”が乗る
COBOLで書かれたシステムの多くは、ドキュメントが整備されておらず、業務知識に密着した“職人コード”になっていることが少なくありません。
つまり、「誰でも触れるコード」ではなく、「経験者でなければ解析できないコード」が広がっているのです。
このようなシステムをメンテナンス・改修するには、COBOLそのものだけでなく、そのシステムや業務に関する“文脈知識”も持っている人材が必要になります。その結果として、より高い報酬が求められるようになってしまうのです。
3. COBOL=レガシー+ミッションクリティカル=“特別対応”
COBOL案件は、そのほとんどが“止められない基幹系システム”に直結しています。たとえば勘定系、請求管理、物流管理など、失敗が許されない業務であるため、一定以上の信頼性・精度・納期厳守が要求されます。
そのため、受託側も「この案件は特殊対応が必要」と判断し、追加コスト(緊急対応・手戻りリスク・属人ドキュメント解析)などを見込んで高単価になる傾向が強いのです。
高騰により企業が抱える現場課題
COBOL人材の単価上昇は、単なるコスト負担だけでなく、経営判断やプロジェクト進行にも影響を及ぼしています。
- 外注予算が確保できず、案件そのものを断念・延期するケース
- 複数のCOBOL系プロジェクトが同時に回せず、優先度で取捨選択を迫られる
- 社内のOB再雇用や、若手エンジニアへの短期引き継ぎなど、苦肉の体制整備
- 定年後の再委託によるセキュリティや継続性への不安
このように、人件費の高騰は単なる経済的問題ではなく、COBOL資産の将来全体に関わる構造課題となっているのです。
出口はあるのか?オフショアによる“現実的な供給戦略”
このような状況の中、企業によっては新たな供給源の確保=オフショアに目を向けるケースも増えています。特に注目されているのが、ベトナムにおけるCOBOL教育と体制構築です。
たとえば、現地大学と連携してCOBOL教育を行い、若手技術者を育成する取り組みや、属人化された既存資産を分解・文書化しながら継承していくラボ型体制の構築など、国内では確保できない若年層COBOL人材を、中長期的に活用できるスキームが少しずつ整いつつあります。
もちろん、品質や言語対応の不安はつきものですが、COBOLに特化したチーム構成や、日本人PMOによる補完体制を構築することで、現実的な選択肢として機能し始めているのです。
まとめ:高騰を課題とするのではなく、体制転換のきっかけに
いかがでしたか?
COBOL技術者の人件費が高騰している背景には、単なるコストの問題だけでなく、COBOLという技術に長年十分な対応がなされてこなかった構造的な課題が横たわっています。
「どうせすぐに移行するから」「そのうち誰かがやるだろう」という先送りの末、人材は減り、継承はされず、今まさに“限界費用”に近い単価で対応せざるを得ない状況に直面している企業も少なくありません。
しかし今あらためて問われているのは、COBOL資産とどう向き合うかという企業の姿勢です。高騰を課題と捉えるだけでなく、持続可能な体制づくりに向けた転機と捉えることが求められています。
中長期的なCOBOL保守体制の確保に向けて、新たな供給源(オフショアや社外パートナー)とどう向き合うかが、この人材難を乗り越えるための重要な鍵となるでしょう。