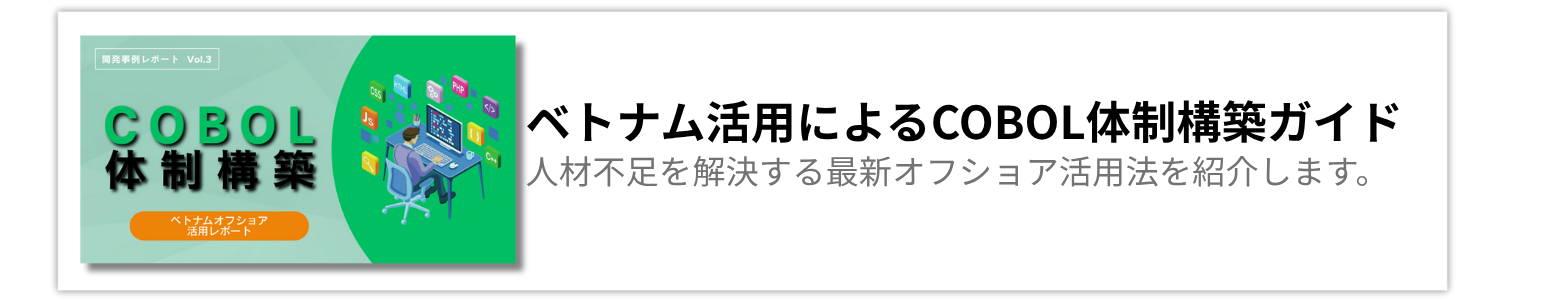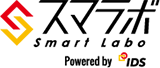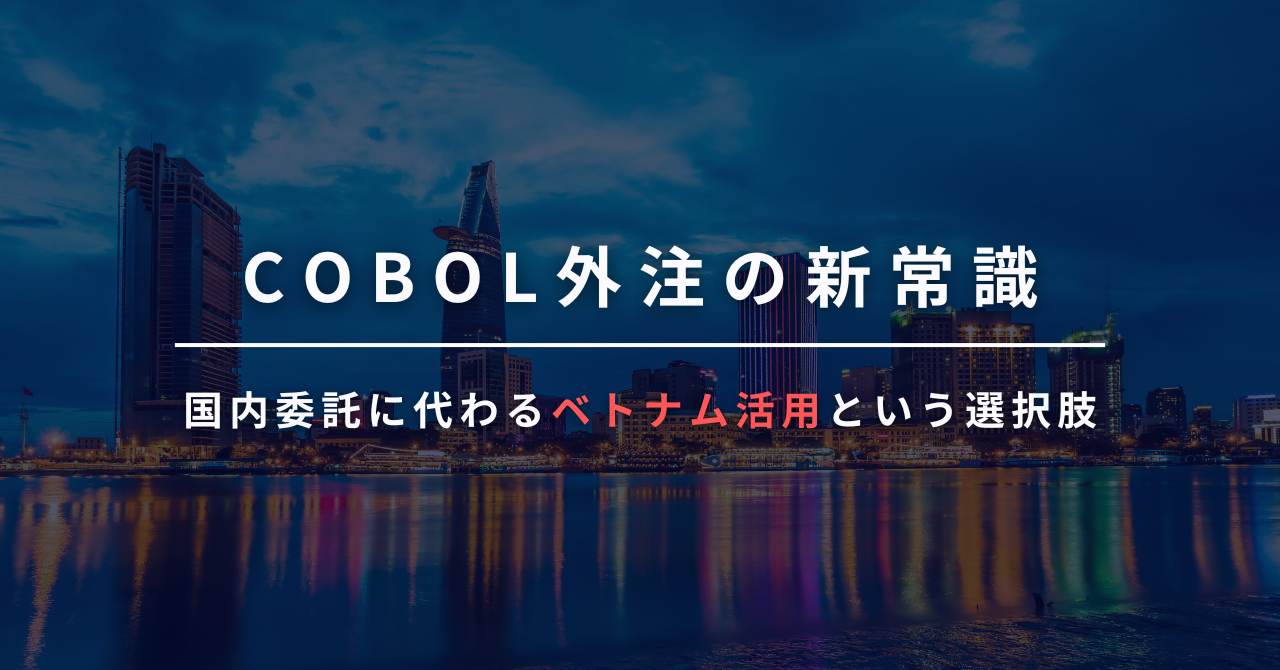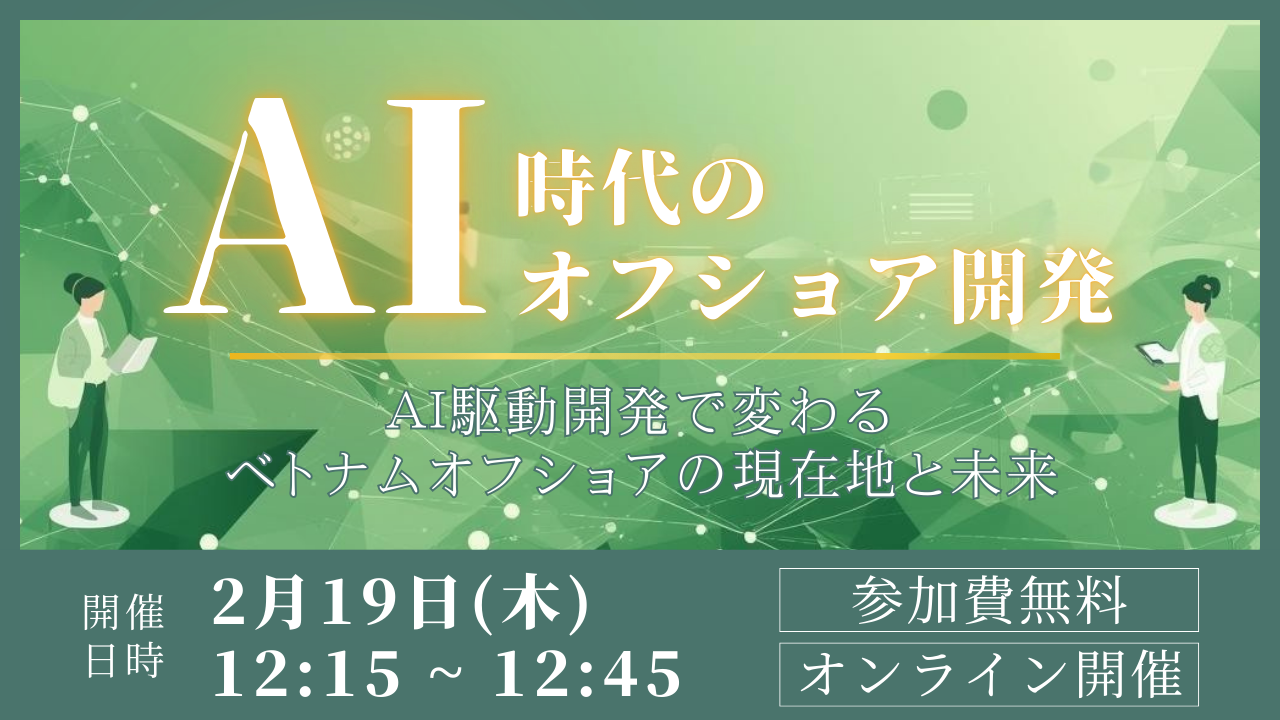COBOLは今なお金融、保険、公共などの基幹システムで広く使われています。しかし、保守を支えるエンジニアは高齢化が進み、引退による人材流出が深刻化しています。若手エンジニアの育成も思うように進まず、「システムは動いているが、社内にノウハウが残っていない」という企業は少なくありません。
こうした状況の中、COBOL保守を外注する企業が増えています。これまでは国内委託が中心でしたが、近年はベトナムをはじめとする海外活用が現実的な選択肢となりつつあります。本記事では、なぜベトナムが注目されているのか、そして海外委託を成功させるためのポイントを整理します。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOL保守を国内で続けるべきか、海外に切り替えるべきか迷っている
- COBOL外注に興味はあるが、海外委託の実態がわからず不安
- 長期的にCOBOL資産を維持する方法を探している
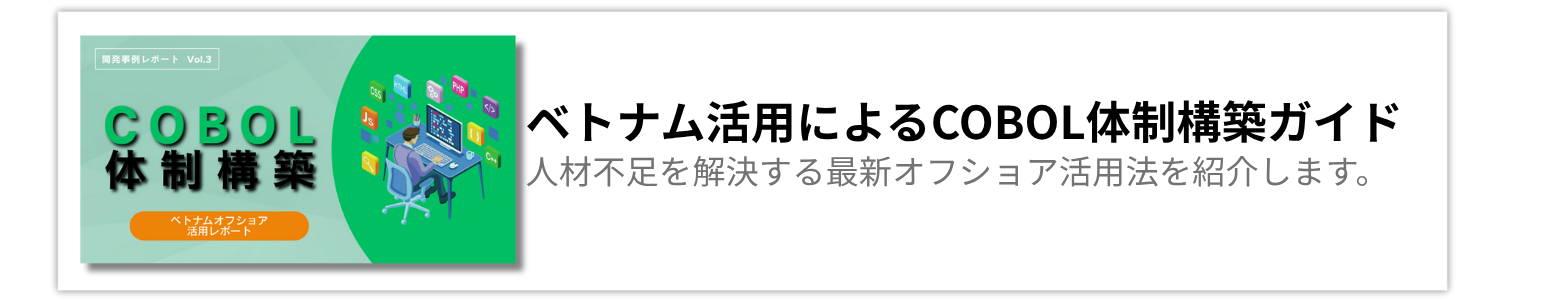
目次
COBOL保守の現状と課題
COBOL保守を取り巻く課題は大きく二つあります。
一つ目は人材不足です。国内でCOBOLスキルを持つ人材は50代以上が中心で、現場を支えるベテランが退職するたびに、システム理解が失われていくケースが多発しています。
二つ目はコストと継続性の問題です。国内委託先は人月単価が高く、依頼できる企業も限られています。仮に保守を継続できたとしても、数年後には体制そのものが維持できなくなるリスクを抱えています。
つまり、COBOL保守の課題は「今なんとか維持できるか」ではなく、「数年先も安定して運用できるか」という点にあります。これが、海外委託を検討する企業が増えている理由の一つです。
なぜベトナムなのか?
海外の中でも、ベトナムは特に注目されています。その理由は主に以下の通りです。
若手人材の供給力
ベトナムはIT教育が盛んで、若手エンジニアの育成に力を入れています。近年ではCOBOL教育プログラムを設ける企業も登場し、COBOL保守を長期的に担える人材を計画的に育てている点が特徴です。
コスト面での優位性
国内委託に比べて人月単価を抑えられるケースが多く、長期契約を前提としたラボ型体制を活用すれば、コストを最適化しながら安定した運用が可能です。
日本向け特化の進展
ベトナムは日本とのIT協力が長年続いており、日本語教育やブリッジSE育成に力を入れる企業が増えています。日本語でのコミュニケーションに対応できるチームが存在することで、仕様確認や障害対応時の認識齟齬が減少しています。
実績の蓄積
特に金融や保険、公共などの分野でベトナム活用の事例が増えています。日本市場に特化したオフショア体制を構築する動きが活発化している点も、他国と比べた優位性です。
ベトナム委託で失敗しないためのポイント
もちろん、ベトナムに限らず海外委託にはリスクも伴います。成功させるためには、以下のポイントを意識することが重要です。
小さく始める
いきなりすべてを任せるのではなく、部分的な保守や調査業務からスタートするのが現実的です。実際の対応品質やコミュニケーションを確認しながら、徐々に範囲を拡大する方法が有効です。
コミュニケーション体制の確認
日本語が話せるブリッジSEや定例ミーティングの有無など、意思疎通の仕組みが整っているかを事前に確認しましょう。仕様書やドキュメントが不十分な場合は、初期段階で整理してもらえるかも重要です。
実績と継続性のチェック
単に「COBOLができます」と言うだけでなく、どの業種・どの規模の案件で実績があるかを確認することが不可欠です。また、担当者の入れ替わりが少なく、長期的に同じチームが維持されるかどうかも重要です。
COBOL保守を見直すなら、今がタイミング
人材不足が進む中、COBOL保守体制の見直しは年々難易度が上がっています。国内委託も選択肢ではありますが、人材供給が安定しているベトナムを活用することは、次世代へのシステム維持という観点で合理的な選択肢です。
ベトナム活用は単なるコスト削減の手段ではなく、「COBOL資産を次世代へつなぐ現実的な解決策」として位置付けられます。海外だからといって構えるのではなく、段階的にテストしながら最適なパートナーを見つける姿勢が求められます。
おわりに:まずは情報収集から始めよう
COBOL保守を国内で続けるか、海外に切り替えるかは、企業のシステム状況や運用方針によって変わります。しかし共通して言えるのは、今動き出すかどうかが将来の安定性を左右するということです。
「具体的にどのような体制でベトナムがCOBOL保守を支えているのか」「どのように段階的に移行できるのか」を知ることが、最初の一歩です。
当社では、ベトナム唯一のCOBOL開発・保全体制について、事例や体制構築のポイントをまとめた資料をご用意しています。COBOL保守の次の一手を検討する際に、ぜひお役立てください。