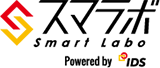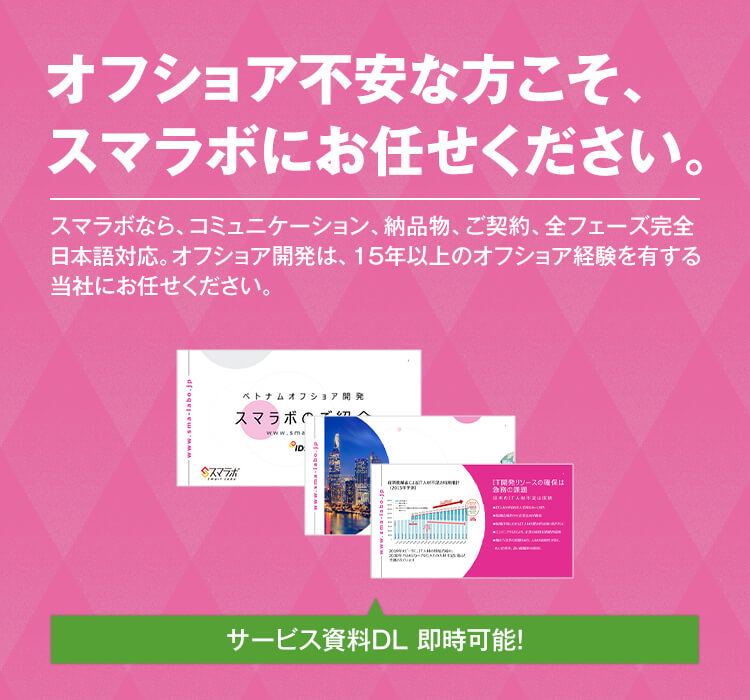COBOLを使用した基幹システムの保守体制に限界を感じていても、「完全な移行には踏み切れない」「今すぐ終わらせるわけにもいかない」という企業は少なくありません。人材不足や属人化が進むなかで、外部のリソースを活用する「外注」は現実的な選択肢となりつつあります。
しかし、COBOLという特殊な技術領域において、外注にはどのような実態やリスクがあるのでしょうか。
本記事では、COBOL保守の外注に関心を持つ企業担当者の方に向けて、COBOL保守を外注する場合の現状と注意点をわかりやすく整理します。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOL保守体制の継続に悩んでいる中堅〜大手企業の技術部門
- 内製メンバーが定着せず、外部パートナーの活用を検討している方
- 中国オフショアからの切り替え先を探しているシステム担当者
目次
COBOL保守はなぜ外注が難しいとされてきたのか
COBOLの外注が一部企業でためらわれてきた理由のひとつに、「対応できる外部パートナーが限られている」という事実があります。COBOLは現在の主流言語とは異なり、若手エンジニアの習得が少なく、ベンダー側の技術者層も高齢化が進んでいます。
また、COBOLが用いられるのは主に金融・製造・公共といった高い信頼性が求められる分野です。そのため、ちょっとした仕様変更でも業務や決済に影響を与える可能性があり、仕様理解と品質管理のハードルが非常に高いのです。外注先が表面的なコードレベルだけでなく、業務文脈まで読み解ける体制でなければ、保守はおろか、トラブル対応すら成立しません。
外注の選択肢は「ある」。ただし体制とパートナーがカギ

一方で、COBOLの保守に特化したサービスを提供している外注先も存在します。国内だけでなく、オフショア開発を活用したコストと体制の最適化を狙う企業も増えています。特に注目されているのが「COBOLに特化したオフショア体制」の構築です。
たとえば、ベトナムなどのオフショア先では、COBOLに関する基礎研修からチーム体制の構築まで行い、「単なる受け身の下請け」ではなく、能動的に保守・改善を進める体制が生まれつつあります。属人化や短期離脱といった国内の内製体制で抱えていた問題に対し、チームでの継続保守という別のアプローチを提示できることは、大きな前進です。
外注で考慮すべき3つのリスク
技術品質と業務理解
COBOL経験者であっても、業務の背景や既存資産の設計意図を把握できていなければ、的確な保守は困難です。属人化した設計や更新履歴が乏しい場合、外部が入り込むことで混乱を招く可能性もあります。そのため、初期段階での引き継ぎ支援とドキュメント整備は欠かせません。
日本語対応とコミュニケーションの壁
特にオフショア開発を活用する場合、技術力と同じくらい重要なのが「日本語での正確な意思疎通」です。仕様変更や障害対応では細かいニュアンスのズレが致命的になりかねません。専任の日本語ブリッジエンジニアを配置するなど、組織としての日本語対応力を見極める必要があります。
契約後の継続性と担当者交代リスク
外注を始めた当初はうまくいっていても、「契約担当者の退職」や「プロジェクトの縮小」によって体制が揺らぐケースがあります。属人的でない体制、例えば複数名による体制構築やスキルマトリクス管理の導入など、継続性を担保する工夫が求められます。
ベトナム唯一の「COBOL保全体制構築サービス」という選択肢
最近では、日本企業のニーズに応えるべく、「COBOLを継続して支えるための専用チーム」をベトナムで構築・運営する取り組みが生まれています。単にコストダウンを目的としたオフショアではなく、「属人化を防ぐ継続保全体制」にフォーカスしているのが特徴です。
特に「中国オフショアからの脱却」を検討する企業にとっては、セキュリティ・ガバナンス面でも安心できる移行先として注目されています。初期検討段階では、「ベトナムでCOBOLができるのか?」という疑問を持たれることもありますが、実際に導入企業の声やトライアル事例を通じて、信頼性を評価する企業が増えています。
おわりに:外注か内製かではなく、“どう維持するか”の時代へ
COBOLを外注するという選択肢は、もはや避けたい最終手段ではなく、「どう維持するか」という戦略的な選択へと変わりつつあります。人材不足、属人化、そして変化に対応するためのスピード。そのすべてに向き合うには、単に人を補うだけでなく、継続可能な体制を設計することが欠かせません。
「COBOLを外注できるのか?」という問いは、「COBOLを、これからどう守っていくか」という問いに変えていくべきなのかもしれません。
COBOLのオフショア開発ならスマラボへ
属人化や人材不足に悩むCOBOL資産、どう守りますか?
「COBOL保守外注の実態と進め方」をまとめた資料を無料でご覧いただけます。
無料で資料を受け取る