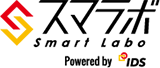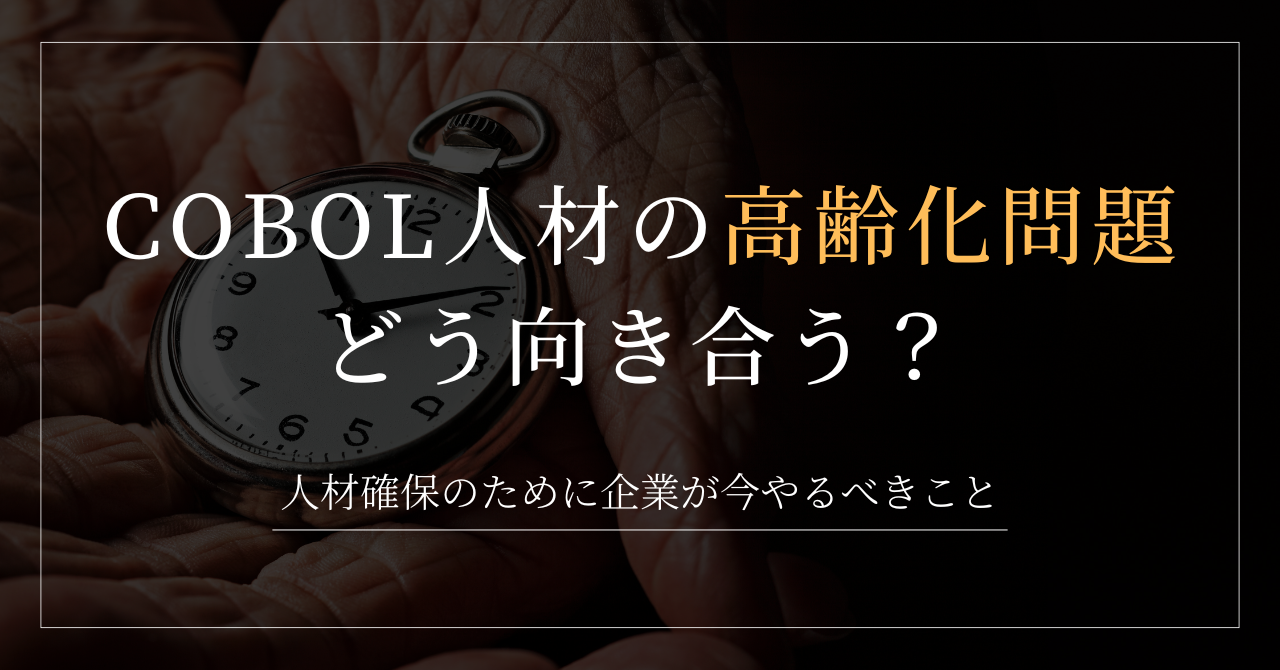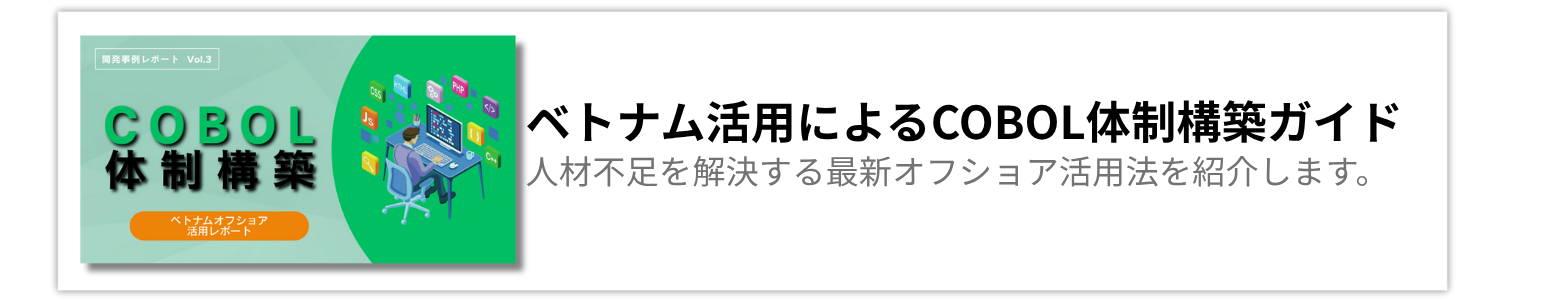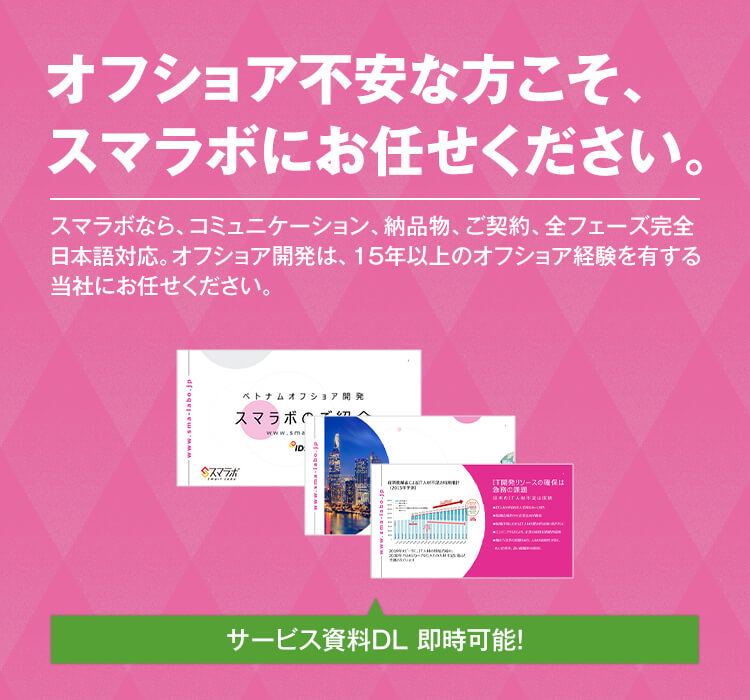こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
「このシステム、あの人にしかわからないんだよね」
長年COBOL資産を保守している現場では、そんな会話が日常のように交わされているかもしれません。特定の社員にしか仕様や構造がわからない、属人化したシステムは、今や日本企業の多くにとって“静かな爆弾”となっています。
その背景にあるのが、COBOL技術者の高齢化です。日本国内でCOBOLに従事する技術者の多くは40代後半〜60代。ある調査では、平均年齢が60歳を超えているとも言われています。つまり、引退や体調不良などによって、予期せぬ人材の離脱がいつ起きてもおかしくない状況なのです。
「気づいたら誰もCOBOLを扱えない」「急にシステムが触れなくなった」という事態は、実際に発生し始めています。保守できない基幹システムが企業の信用や事業継続に直結することを考えれば、これは一部のIT部門の課題ではなく、経営レベルでのリスクと捉えるべきです。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOL資産の保守体制に不安を感じている
- 若手エンジニアのCOBOL離れに課題を感じている
- 社内での継承に限界を感じ、外部パートナーの活用を検討している
▼COBOL人材の確保に限界を感じている方へ|長期安定のCOBOL保守体制を資料で解説しています▼
目次
なぜCOBOLは“切り替えられない”のか? ― 維持が前提の現実

では、「COBOLが問題なら、いっそ最新技術に置き換えてしまえばよいのでは?」という考えが浮かぶかもしれません。確かに、クラウド化やモダナイゼーションを模索する企業は増えています。しかし、実際にそこに踏み切れる企業はごく一部に限られています。
なぜなら、COBOLが稼働しているのは、受発注、会計、人事、金融処理など、企業の根幹部分に関わる重要システムだからです。これらをモダンな環境に移行するには、莫大なコストと時間、さらに業務理解と詳細な仕様分析が不可欠。しかも、長年運用されてきたがゆえに「設計書がない」「コードの意味が誰にもわからない」という属人化された状態も珍しくありません。
このような状況の中で、無理にマイグレーションを進めると、かえってトラブルや業務停止リスクを生むことになりかねません。その結果、COBOLを残しながら維持するという現実的な判断をする企業が大半なのです。
社内育成は現実的か? ― 継承がうまくいかない理由

「COBOL人材の高齢化が進むなら、社内で若手を育てていけばいい」。一見もっともなこの考えも、実行に移すとなると大きな壁があります。
まず、若手がCOBOLに魅力を感じていないという現実があります。現在のエンジニア志望者は、クラウドネイティブやAI、Web3など“トレンド技術”に強い関心を持っています。キャリア形成の観点から、COBOLは「古くさい」「将来性がない」と見られ、敬遠されがちです。
さらに、教育リソースの問題も深刻です。現場でCOBOLを扱える社員がすでに少ない中で、教育係として若手を指導する余力がありません。手順書も十分ではなく、OJT頼みの継承は非効率になりがちです。「教える人も、教わる人もいない」この負のループが、多くの企業でCOBOL継承を停滞させています。
加えて、育成が進んだとしても、その人材が数年後に会社に残っている保証もないというジレンマもあります。せっかく育てた若手が「やっぱりモダンな環境で働きたい」と離職するケースもあり、企業は継承に踏み出せずにいます。
今こそ考える“外の手” ― 高齢化リスクに備える選択肢

こうした状況を踏まえると、社内だけでCOBOL体制を完結させるのは、もはや限界に近づいています。そこで有力な選択肢となるのが、外部パートナーを活用した体制構築です。
国内では、COBOL技術者が引退を迎える中で外部リソースの奪い合いも起きており、コストも高止まりしています。そこで注目されているのが、海外(特にベトナム)でのオフショア体制構築という方法です。
ベトナムでは、地方大学と連携してCOBOLを専門に学ぶ教育カリキュラムを実施する動きが始まっており、実務教育を受けた若手人材を育成・供給する仕組みが整いつつあります。日本語教育や日本の商習慣に関するマナー研修も含まれており、日本企業との親和性が高いCOBOL人材の確保が可能になってきました。
さらに、プロジェクト管理や品質管理も日本側が主導できる体制が整備されており、「オフショア=丸投げで品質が不安」という不安も払拭されつつあります。
▼こちらの記事でオフショア開発の実態とリスクについて詳しく解説しています▼
COBOL保守は外注できるのか?実態とリスクを解説
まとめ: “いま何を始めるか”が未来を変える
「そのうち何とかしないと」と思いながらも、手をつけられていない企業は多いはずです。
しかし、COBOL人材の高齢化は待ってくれません。今何も手を打たなければ、数年後には「誰も触れない資産」だけが残ってしまうという最悪の状況に陥りかねません。
まずは、一部のサブシステムや帳票改修といった限定的な範囲で、外部引き継ぎや教育付きのトライアルチームを立ち上げることから始めてみてはいかがでしょうか。実際に動かしてみることで、リスクやハードルも明確になり、より現実的な体制構築が可能になります。
特に、ベトナムのように教育・採用・日本語対応が整っている拠点と連携すれば、属人化のリスクを低減しつつ、将来的に自律した保守運用体制へと進化させることも視野に入れられます。
“今できること”を見極め、小さくても確実な一歩を踏み出すこと。それが、5年後の事業継続性を左右する分岐点になるのです。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
▼ COBOL人材の確保に限界を感じている方へ |長期安定のCOBOL保守体制を資料で解説しています▼