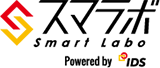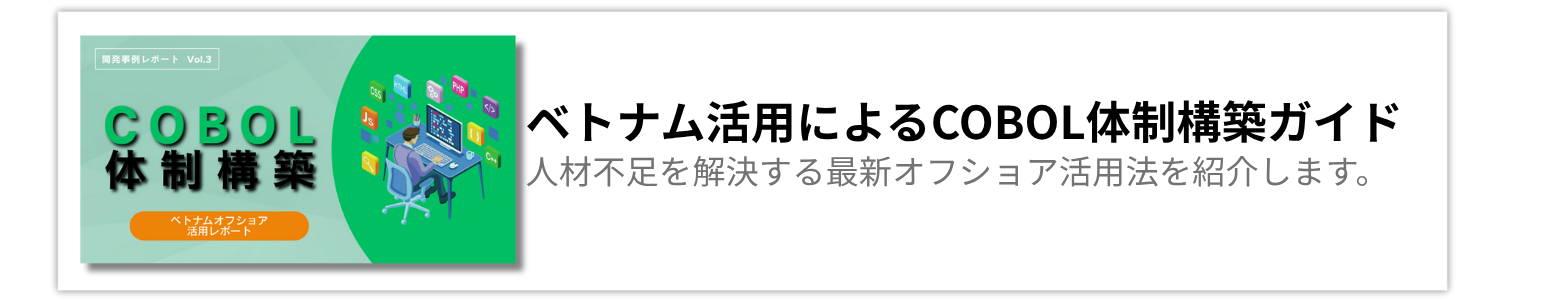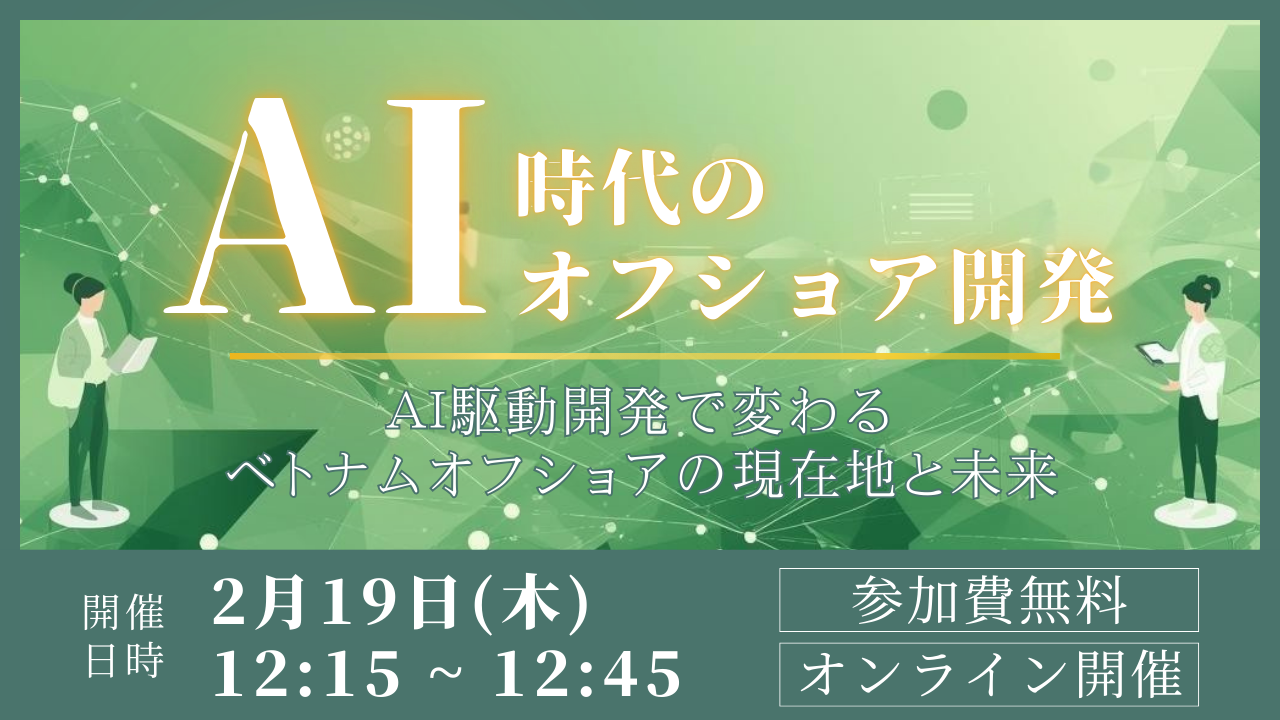こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
近年、「COBOLは古い技術だから、いずれ消える」といった前提で議論されることが少なくありません。
実際、多くのITベンダーやコンサルティング会社が、刷新やマイグレーションを強く推奨し、「このまま放置すると業務が止まる」と警鐘を鳴らしています。
しかし、そうした言説の前提には、“古いもの=不要なもの”という暗黙の価値観があります。
前編で紹介したように、COBOLで構築されたシステムは今もなお多くの企業や行政機関で現役稼働しており、業務を支える要の役割を果たしています。
このような現実を無視して、「捨てるべき」「変えるべき」と結論づけるのは、本当に合理的なのでしょうか。
むしろ、現実的に見れば、「残す」という判断には明確なメリットがあり、それを支える仕組みさえ整えれば、企業にとっては“最もリスクの少ない選択”になり得るのです。
この記事では、「COBOLを残す」という選択肢に焦点をあて、なぜそれが現実的なのか、どのように体制を整えていくべきかを整理していきます。
まだご覧になっていない方は、前編「なぜCOBOLは使われ続けているのか?」はこちら からご確認ください。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOLを「残す」ことに不安を感じながらも現場では必要性を感じている
- マイグレーション以外の現実的な選択肢を検討中
- 属人化の解消や人材確保の方法に悩んでいる
目次
「残す」ことで得られる合理的な価値とは

COBOLをあえて残す選択をした企業は、過去にしがみついているのではなく、目の前の現実に対して最適な打ち手を選んでいるに過ぎません。
まず第一に、COBOLを残すことによって、既存システムをそのまま活かすことができ、業務を止めずに済みます。
特に基幹系システムは他の業務と密接に連動しているため、一部を改修しただけで全体が影響を受ける危険性があります。その点で、「安定稼働を保ちながら必要な改修だけを行う」というアプローチは、業務継続性を守るという観点からも非常に有効です。
また、必要な部分にだけ手を加えられるという点は、コスト面でも優れています。刷新では数千万円〜数億円規模の予算が必要になる一方で、保守・改修ベースであれば段階的な対応が可能です。現場の柔軟な意思決定にもつながり、予算やリソースの制約がある企業にとって現実的な解決策となります。
さらに、COBOL資産を活かしながら徐々に刷新を進めていくという“ハイブリッド戦略”も現実的な選択肢です。完全刷新を急ぐのではなく、既存のCOBOL環境を維持しつつ、周辺業務やフロント側から段階的にモダナイズしていく。このやり方であれば、リスクとコストのバランスを取りながら、将来への移行準備を進めることができます。
維持に必要なのは「仕組み化された体制」

もちろん、「残す」だけでは問題は解決しません。
最大の障壁は、COBOLを理解できる人材が減り続けているという現実です。
保守経験者が次々に定年退職し、引き継ぎが間に合わず、属人化のリスクが深刻化しています。中には「COBOLを触れる人がもういない」という企業も出てきています。
このような状況において、COBOL資産を安全に維持していくためには、体制の再構築が不可欠です。
まずは、属人化を排除するためにドキュメント整備を行う必要があります。
設計書や運用マニュアルが散逸していたり、紙ベースで更新されていないケースも多いため、システム全体の仕様を見える化し、誰が見ても理解できる状態にしておくことが求められます。
加えて、社内で人材が確保できない場合は、外部の力を借りるという判断も現実的です。
一昔前までは、COBOLを扱える外部リソースといえば国内派遣が主流でしたが、近年ではベトナムなどのオフショア開発拠点でCOBOL人材を育成・確保する事例が出てきています。
▼こちらの記事で、COBOL人材の高齢化問題についても詳しく解説しています▼
COBOL人材の高齢化問題、どう向き合う?企業が今やるべきこと
ベトナム発の「COBOL人材スキーム」という新たな可能性

「ベトナムにCOBOLエンジニアなんているのか?」と思われる方もいるかもしれません。
実際には、ベトナムでは大学と連携したCOBOL教育が始まっており、若手エンジニアの継続的な育成と採用が仕組み化されたスキームが生まれつつあります。
たとえば、タインホア省のHong Duc大学では、3年次からCOBOLプログラミングを学び、インターン期間中に実務ベースの保守業務にも取り組みます。
卒業後には、日本向けに特化したオフショア開発企業に入社し、COBOL保守チームの一員として本格的にキャリアをスタートさせます。
このスキームには、日本語教育やビジネスマナー教育も含まれており、日本人PMOや通訳との連携のもと、要件確認や品質管理を高いレベルで担える体制が構築されています。
従来の「オフショアはモダン技術の開発のみ」といった認識を覆し、COBOLの保守をベトナムで支える時代が到来しつつあるのです。
▼こちらの記事で、ベトナム人材を活用したCOBOL保守について詳しく解説しています▼
COBOL外注の新常識:国内委託に代わるベトナム活用という選択肢
「残し方」を選べる時代へ:COBOL保守の3つの体制
COBOLを残すと決めたとき、どのように体制を整えるかは企業ごとに異なります。
ただ、選択肢が増えている今だからこそ、自社の事情に合った進め方を考える余地があります。
たとえば、社内にノウハウが残っている企業であれば、一部の業務をベトナム側に段階的に委託しながら、属人化の解消と人材育成を並行する「共同保守型」が有効です。これは、自社で要件定義や設計を行い、コーディングやテストをオフショアに任せるスタイルです。
一方で、属人化が進みすぎている場合や、人材リソースの不足が深刻な企業では、早い段階から「段階的移管型」や「自律保守型」といった、よりオフショア主導の体制に移行することも選択肢となります。
これらの選択肢は、決して一律の正解があるわけではありません。大切なのは、“COBOLを残す”という方針を前提にしながら、それにふさわしい体制を柔軟に構築する視点を持つことです。
“消すこと前提”から、“活かすこと前提”への転換
2025年の崖が目前に迫るなかで、COBOL資産をどう扱うかという問いに、多くの企業が向き合い始めています。
これまで、「レガシー=時代遅れ」という印象だけで語られてきたCOBOLですが、実際には今も現場で稼働し、改修され、価値を生み出している技術です。
もしそれを「なくす前提」で議論し続けるなら、企業は大きな混乱や失敗を招くかもしれません。
いま必要なのは、「どう活かすか」「どう継承するか」「どう残しながら変えていくか」といった、維持と変化を両立させる視点です。
この視点に立つことで、COBOLを“過去の負債”ではなく“現在の資産”として捉え直すことができるようになるはずです。
まとめ:COBOLを残すなら、残す覚悟と体制を
いかがでしたか?
COBOLは確かに古い技術です。しかし、それが「使ってはいけない」ことを意味するわけではありません。
むしろ、堅牢で信頼性が高く、大量データ処理に向いているという利点を持っており、現代の業務にも適したシーンが多く存在しています。
そして、今問われているのは、「使い続けていいか」ではなく、「どう使い続けるか」という問いです。
その答えの一つが、「維持できる体制を構築する」という考え方です。
属人化を防ぎ、外部と連携し、人材を育成し、COBOL資産を支える仕組みを整える。
この地に足のついた取り組みこそが、2025年以降の“崖を超える方法”となるのではないでしょうか。
▼COBOL資産の維持をお考えの方へ。教育・継承を支えるオフショア保守体制をご紹介中!▼