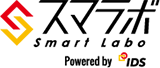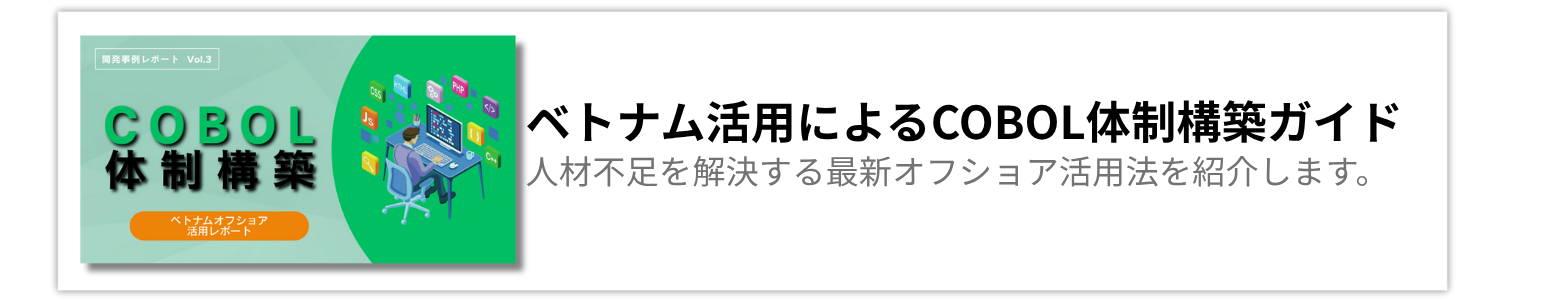こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
前編では、「2025年の崖」がもたらす最大のリスクは“技術の古さ”ではなく、“それを扱える人がいなくなること”であると述べました。
つまり、IT人材の高齢化と属人化が進行する中で、COBOLなどのレガシー資産は、今すぐ“刷新”するか、さもなくば“崖から落ちる”という単純な二択ではありません。
実際には、その中間にあたる“現状を延命・維持しながら次の一手を整える”という第三の道も存在します。
後編では、この「COBOL資産を捨てずに守る戦略」について深掘りしていきます。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOL資産を捨てられず、どう維持すべきか悩んでいる
- マイグレーション以外の選択肢を模索している
- 属人化と人材不足によりCOBOL保守の継続性が危ういと感じている
▼前編では「2025年の崖」の構造的な問題や、“マイグレーション神話”に潜む誤解について解説しています。▼
IT人材70万人不足時代へ——2025年の崖とは何か?構造的問題と見えていない本質(前編)
目次
COBOL資産が残る企業のリアル:なぜ移行できないのか?

マイグレーションが進まない理由は、単にコストや工数の問題ではありません。実際の現場では、以下のような課題が複雑に絡み合っています。
●完全なドキュメントが存在しない
多くのCOBOLシステムは、30年以上前から稼働し続けており、仕様書が紙ベースで一部しか残っていない、あるいは当時の担当者にしか仕様がわからないというケースも珍しくありません。
●経営判断としての優先順位が低い
企業にとってITは“手段”であり、“主戦場”ではないことが多くあります。日々の事業運営に支障がなければ、莫大なコストをかけてシステムを刷新する意義を、経営層が見出せないのも無理はありません。
● 法制度や業務固有要件との密着性が高い
レガシーシステムは、個社ごとの細かな業務仕様や法律対応を積み上げてきた結果、極めてカスタマイズされた構造になっています。パッケージへの単純な置き換えが困難なため、移行自体が重いプロジェクトになります。
“維持と継承”という現実的な戦略 なぜレガシーシステムは簡単に“捨てられない”のか?

上記のような事情がある企業にとって、「COBOL資産をどう維持するか?」は単なる一時しのぎではなく、中期的に必要な戦略になります。
その戦略の柱となるのが、「属人化の排除」「人材の補充・育成」「業務知識の移転」の3点です。
① 属人化の排除
現行の担当者が突然離任しても大丈夫なように、第三者がソースコードを理解し、保守できる状態にしておく。ドキュメント整備やソースの構造化が重要になります。
② 人材の補充・育成
社内だけでなく、外部のCOBOLスキルを持つ人材を確保する体制づくりが求められます。中長期的には、若手人材を教育し、一定のレベルに引き上げることが不可欠です。
③ 業務知識の移転
コードだけではなく、運用ルールや業務フローの知見も属人化していることが多いため、それを体系的に伝承できる環境構築が必要です。
これらを実現するには、外部の知見を活用する仕組みが効果的です。そこで注目されているのが、オフショア拠点を活用したCOBOL保守の体制構築です。
ベトナムでのCOBOL維持体制構築という選択肢

「COBOL × オフショア」と聞くと、不安を感じる方もいるかもしれません。「もう誰もCOBOLなんて学ばないのでは?」「文化も言語も違う相手に任せられるのか?」という疑問も当然です。
しかし実は、その前提は変わりつつあります。
ベトナムでは、ある企業が公立大学と連携し、学生時代からCOBOLを学ばせる教育スキームを整えています。3年次からCOBOLの基礎教育を開始し、卒業前には実務トレーニングと品質管理研修までを経て、実践対応が可能な人材を育成しています。
加えて、次のような仕組みも整っています:
- 日本語教育/日本式マナー教育の実施
- ベトナム側での翻訳者・ITコミュニケーターの常駐
- 日本人PMOの補佐体制とオフショアブリッジSEの育成
これらの取り組みによって、現場で求められるレベルの品質・納期・言語対応を備えた、“COBOLを維持する体制”が現実のものとして提供可能になっているのです。
ベトナム×COBOL体制の具体イメージ
実際の運用では、以下のような3ステップでの導入が効果的です。
ステップ1:一部領域のナレッジトランスファー
ドキュメントの整備や、ベトナム側チームによるシステムの理解を目的とした段階。ここでは、属人化を排除するための整理が行われます。
ステップ2:共同保守体制の確立
国内担当者とベトナム側のチームが連携しながら、小規模な改修や運用保守を通じて業務・技術の理解を深める。翻訳者や日本人SEが品質管理を補佐します。
ステップ3:業務継続を支える保守基盤へ
段階的に業務を移管しながら、体制を本格化。ブリッジSEが常駐したり、大学連携による若手追加供給を行うことで、永続的なCOBOL体制が形成されます。
こうした段階的な導入により、「引き継ぎたいけど、教える人がいない」という企業のジレンマを解消することができます。
COBOLを“守る”という選択の意味

「時代遅れだから、捨てる」ではなく、「続けるから、守る」。
この発想の転換こそが、2025年の崖を前にした現実的かつ持続的な判断だと私たちは考えます。
COBOLの保守を自社単独で継続するのが難しい企業は、外部との連携を前提とした“分散型の保守体制”を模索する必要があります。
そしてその体制が、属人化のリスクを回避し、刷新の準備期間を生み出すことにもつながります。
さらに、COBOLを“活かす”ことで得られる最大の価値は、「安心して変えられるタイミングを選べる」という経営上の柔軟性です。
マイグレーションを急いで失敗するのではなく、変えない間も事業を止めないということに、COBOLの価値は残されています。
まとめ:崖の前に、立ち止まる選択肢を
いかがでしたか?
2025年の崖を「刷新」だけで乗り越えるのは、現実的に難しい企業が多数存在します。
だからこそ、今こそ必要なのは「変えない準備」の選択肢です。
ベトナムのようにCOBOLに特化した教育と保守体制を整えた拠点と連携し、「維持」と「継承」を先に整えておくこと。
それが、崖を飛び越えるのではなく、橋を架けるように一歩ずつ移行する道につながっていきます。
▼COBOL資産の維持をお考えの方へ。教育・継承を支えるオフショア保守体制をご紹介中!▼