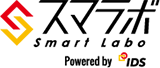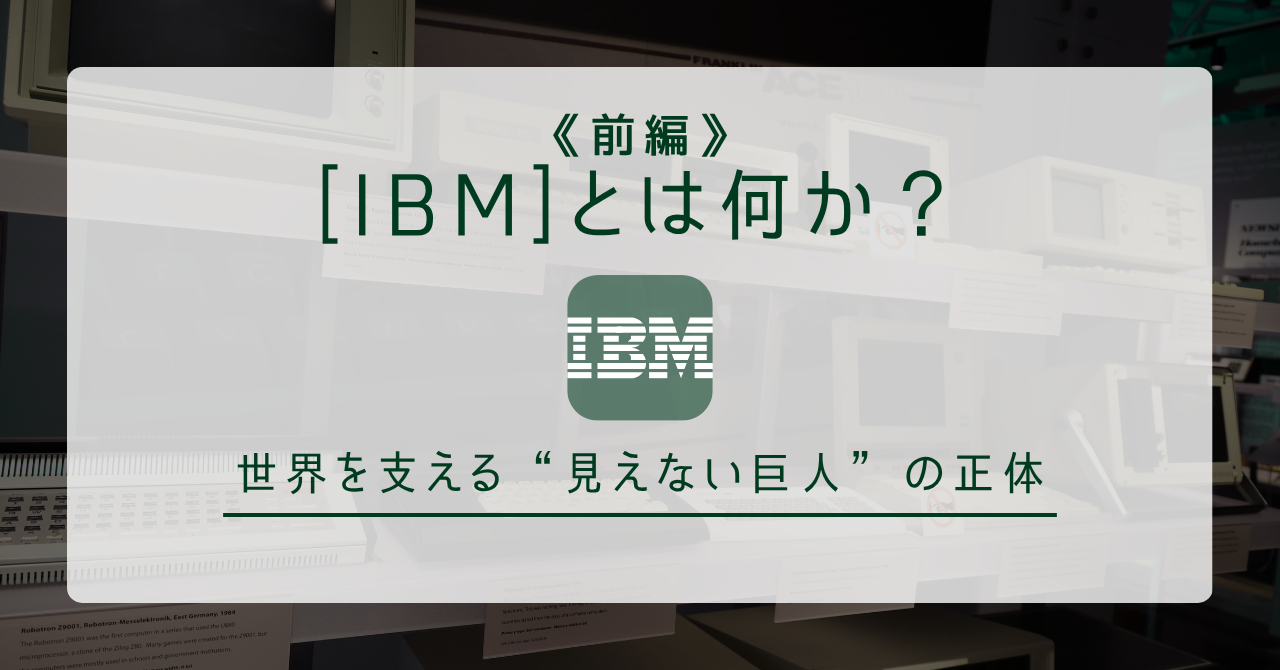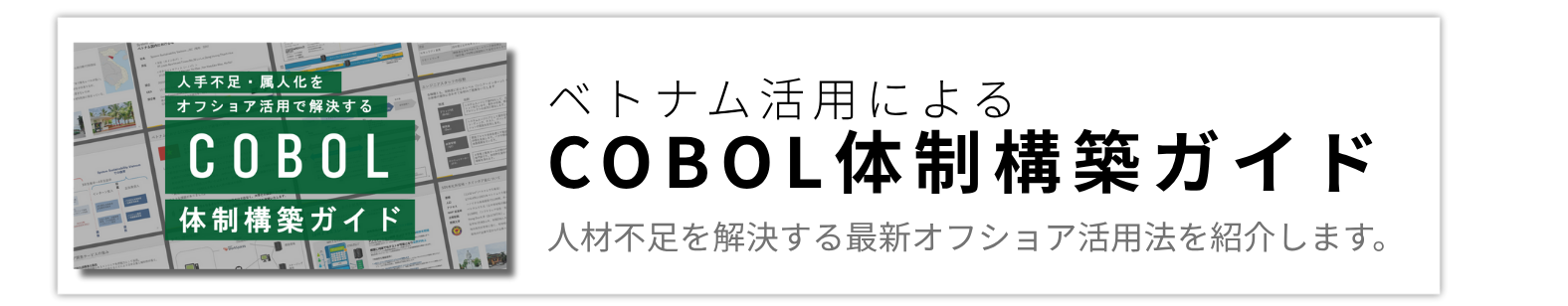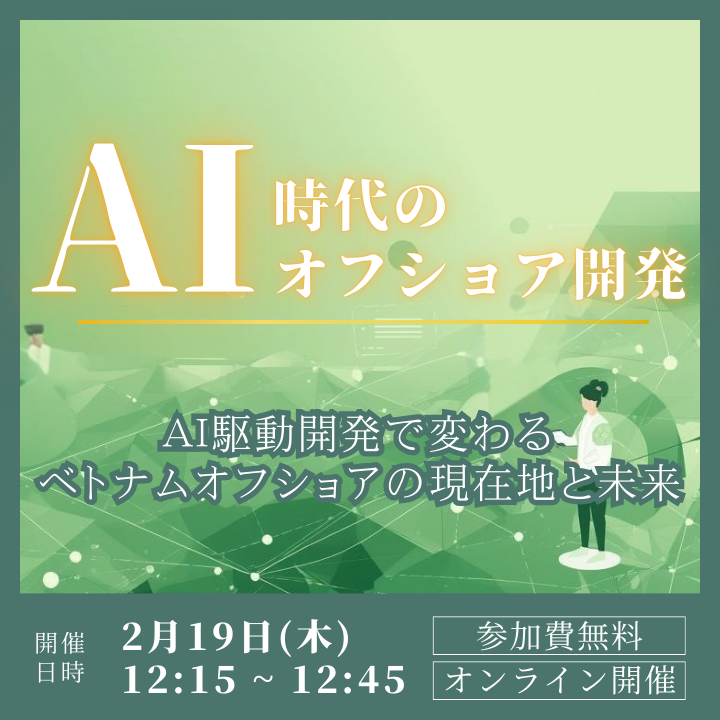AWSやGoogle Cloudが話題を独占するこの時代、IBMという名前を聞くと「昔の会社では?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、世界中の金融・保険・行政など、社会の根幹を動かしているシステムの多くはいまもIBMの技術の上に成り立っています。
そしてCOBOLという言語が今なお使われ続けている理由の一つも、実はこのIBMにあります。
本記事では、IBMとはどんな企業なのか、なぜCOBOLと深く関わってきたのかを整理していきます。
この記事はこんな人にオススメ!
・IBMやメインフレームという言葉は聞いたことがあるが、実際にどんな役割を担っているのかを知りたい方
・COBOLが今も使われ続けている背景を、技術と歴史の両面から理解したい方
・今後のCOBOL保守やオフショア体制構築を検討するうえで、IBM環境の基礎を押さえておきたい方
目次
IBMの成り立ち

IBMの歴史は、コンピュータが生まれるずっと前に始まります。
911年にアメリカで設立された「Computing-Tabulating-Recording Company(CTR社)」が前身で、後に「International Business Machines(IBM)」と改名しました。
当初はパンチカード集計機やタイプライターなど、データ処理を自動化する“ビジネス機械”を製造する会社でした。
これが「Business Machines(業務用機械)」という名前の由来です。
1960年代、IBMは「System/360(システム360)」という画期的な大型コンピュータを開発します。
このシリーズが「メインフレーム(大型汎用機)」というカテゴリーを確立し、世界中の企業や政府機関が採用しました。
その時代、事務処理用として使われ始めたプログラミング言語がCOBOL(コボル)です。
IBMのメインフレームとCOBOL

メインフレームとは、今でいうクラウドの先祖のようなものです。
複数の端末が1台の巨大なコンピュータに接続し、集中管理する仕組みです。
銀行の入出金、税金の計算、保険の契約処理など、国や企業の“根幹業務”を扱うには理想的な構成でした。
このメインフレーム上で広く使われたのがCOBOLです。
COBOLは「Common Business-Oriented Language」の略で、業務向けに設計されたプログラミング言語。
人間が読みやすい構文を持ち、数字や帳票の扱いに強いという特徴がありました。
IBMはこのCOBOLを早い段階で自社のメインフレームに組み込み、“IBM=COBOLの主戦場”という構図をつくります。
今日に至るまで、銀行・自治体・製造業の多くのシステムがIBM製メインフレーム上でCOBOLを実行しています。
以下の記事で、COBOLが使われている業界、企業について分析・解説しています。
《COBOLはどこで生きているのか?金融・行政・企業のリアルを徹底分析》
IBMが強い理由

ITの世界では「古い=劣っている」と見られがちですが、IBMのメインフレームには今なお揺るがない強みがあります。
1.圧倒的な信頼性
IBMのメインフレームは数十年単位で止まらない設計思想を持っています。
障害や災害時にも稼働を維持できるため、金融機関では他の選択肢がほぼありません。
2.後方互換性
30年前に作られたCOBOLのプログラムを、最新のIBM Zマシンでもそのまま動かせます。
つまり「古いコードが資産として生き続ける」という極めて珍しい環境です。
3.安全性と運用ノウハウ
IBMは長年にわたって、厳格なアクセス管理・監査・暗号化技術を標準化してきました。
特に金融や行政分野では「IBM=信頼できる」というブランドが今も根強い理由です。
これらの特徴から、IBMメインフレームは「止められないシステムを動かすための唯一の選択肢」として生き残り続けています。
IBMは今どこに向かっているのか

かつて「ハードウェアの巨人」と呼ばれたIBMは、21世紀に入り大きな転換を遂げました。
サーバー販売だけでなく、クラウド・AI・コンサルティングの総合IT企業へと変化しています。
現在は「IBM Cloud」や、買収した「Red Hat」によるハイブリッドクラウド事業を強化。
またAI分野では「Watson(ワトソン)」を中心に自然言語処理やデータ分析のソリューションを展開しています。
それでも、IBMの基盤事業であるメインフレーム(IBM Zシリーズ)は健在です。
むしろ、クラウドと連携させて“ハイブリッド基幹システム”を構築する方向に進化しています。
古い技術を維持するだけでなく、「新しい仕組みと共存させる」ことがIBMの強みと言えます。
COBOLとIBMの関係を整理する
COBOLは1959年に誕生しましたが、その標準化や普及の中心にいたのがIBMでした。
IBMがCOBOLコンパイラを自社製品に組み込み、教育・支援体制を整えたことで、世界中の企業が採用。
今もIBMはEnterprise COBOL for z/OSという最新バージョンを提供し続けています。
日本の多くのCOBOLシステムも、実はIBM Z(z/OS)環境で稼働しています。
これが「COBOLを刷新できない理由」の一つでもあります。
システムを動かすハードウェアがIBM製で、ソフトウェアもCOBOLで書かれている――この組み合わせが安定しすぎていて、簡単には他のプラットフォームに移せないのです。
おわりに
IBMは“過去の遺産を抱えた企業”ではありません。
むしろ、過去の技術を動かし続け、社会のインフラとして維持している“見えない巨人”です。
COBOLが今も現役で使われているのは、IBMがメインフレームという「止まらない環境」を守り続けているから。
新しい技術が次々と生まれる中で、「変わらないものを動かし続ける力」こそ、IBMが世界から信頼される理由なのです。
COBOL保守体制構築サービスのご案内
本記事でご紹介したIBMとCOBOLの関係、そして日本の基幹システムを支えるメインフレーム環境の背景を踏まえ、当社ではベトナムにおけるCOBOL保守体制の構築支援を行っています。
資料では、Hong Duc大学との教育連携モデルをはじめ、COBOL専門チームの育成プロセス、IBM Zエミュレーターを活用した開発環境、自治体向けの導入事例などを掲載しています。
現地と日本をつなぐ品質管理・セキュリティ体制も含め、持続可能なCOBOL保守の仕組みを詳しくご紹介しています。
ぜひ無料でダウンロードのうえご覧ください。
次回予告(後編へ)
IBMという企業の成り立ちと、COBOLがどのようにメインフレーム上で活躍してきたのかを見てきました。
次回の後編では、その延長として「IBM Z環境をどう扱うか、そしてオフショアでどのように再現しているのか」に焦点を当てます。
- なぜ日本の多くのCOBOL資産がIBM Z上で動いているのか
- エミュレーターを使った開発・検証環境とはどんな仕組みか
- オフショアでもセキュリティと品質を両立する体制はどう作られているのか
技術者にとっては環境設計のリアルを、マネージャーにとっては運用体制の可能性を掴める内容です。
《IBM COBOL環境を再現する ― オフショア開発の新しい現実》