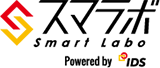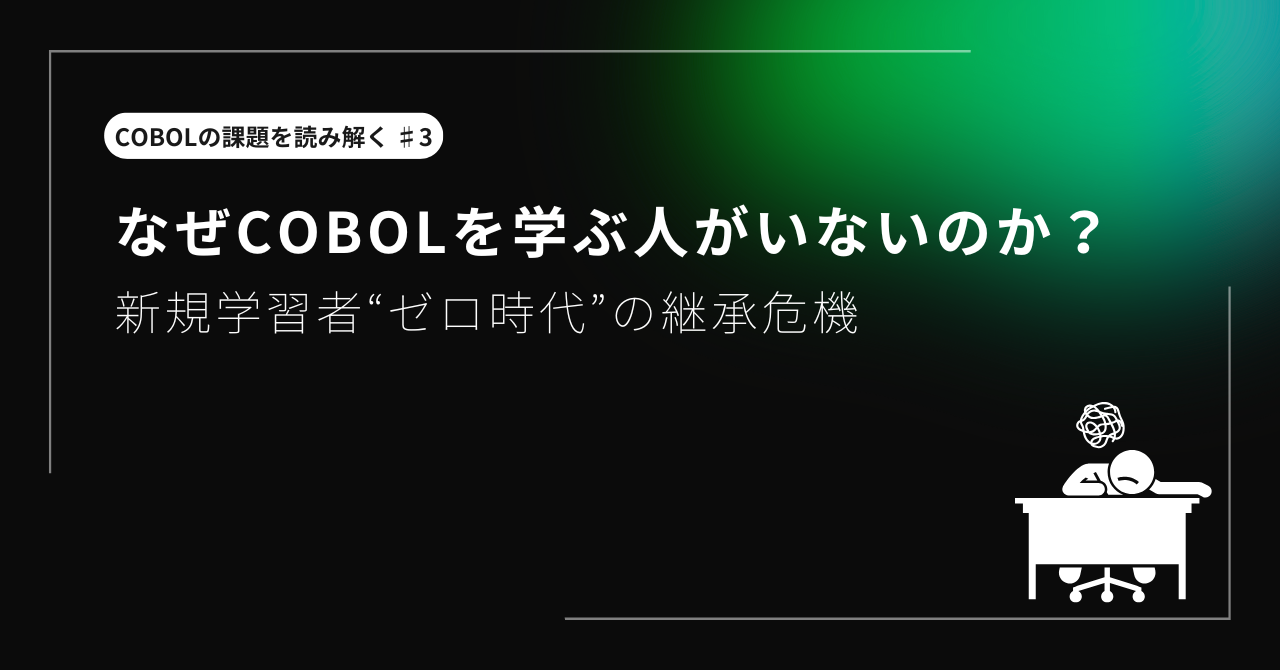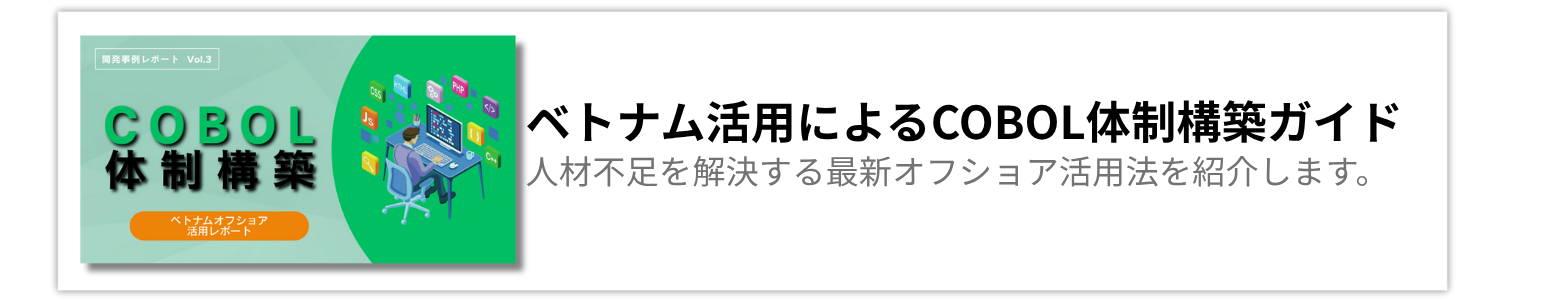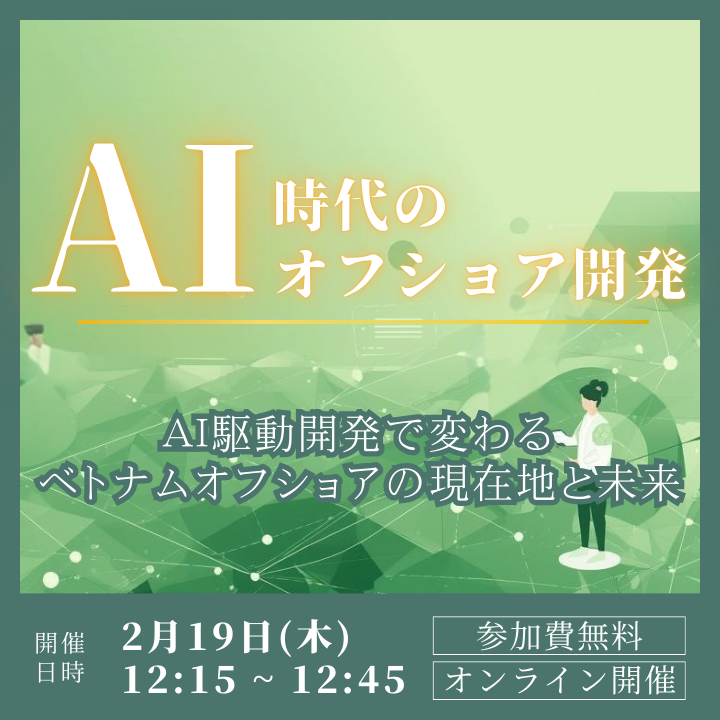COBOL人材不足の背景には、単なる高齢化や人件費の高騰だけでは語りきれない、より根深い構造的な問題があります。それは「新しく学ぶ人がいない」という現実です。どれだけ熟練の技術者が現場にとどまっていたとしても、その知見が継承されなければ、技術や運用ノウハウは時間とともに消失していきます。
COBOLは、日本の社会インフラを支えるシステムの根幹に関わる技術であり、銀行、保険、行政など、広範な領域で今なお現役で稼働しています。その一方で、新たにこの技術を学ぼうとする若手がいないというのは、単なる人材不足というより「継承不能リスク」という側面で捉えるべき深刻な課題です。
本記事では、なぜCOBOLが若手に学ばれず、次世代人材が生まれてこないのかを整理しながら、これからの継承の仕組みづくりについて考察します。COBOL資産を保有する企業にとって、未来の“担い手”がいないという事実に、どう向き合うべきかを見直すきっかけとなれば幸いです。
この記事はこんな人にオススメ!
COBOL保守をベテラン社員に依存しており、今後の引き継ぎに不安を感じている
システムの仕様書がなく、運用が“担当者の記憶頼み”になっている現場を改善したい
属人化のリスクを回避し、チームで対応できるCOBOL運用体制を検討している
目次
なぜCOBOLは“学ばれない”のか?
COBOLが学ばれない最大の理由は、IT人材を育成する教育の場から消えているからです。現在、国内の大学や専門学校において、COBOLを体系的に学べるカリキュラムを提供している機関はごくわずかであり、多くの学生がPython、Java、JavaScriptといった“モダンな”言語に触れています。これは「現場で使われているから」というよりも、「就職に有利」「モダンで転職にも強い」といった実利的な理由に基づいて選ばれていることが多いのです。
また、学生にとってCOBOLという名前自体がそもそも“知られていない”という現実もあります。SNSやQiita、Zennといった情報発信メディアでは、COBOL関連の投稿はほぼ皆無に近く、「情報が見えない=存在しない」と認識されてしまう傾向にあります。
企業からのニーズとしてCOBOLが残っていたとしても、それが学生や若手エンジニアに伝わることはほとんどありません。たとえば「COBOL経験者優遇」と書かれた求人を見た若手が、「今からCOBOLを学ぼう」と思うかといえば、答えはほぼノーでしょう。
さらに、学習コストや開発環境へのアクセスの難しさも障壁です。COBOLをローカル環境で動かすには専用の開発環境やランタイムが必要であり、Webブラウザ上でサクッと試せるような仕組みが整っていません。結果的に、「興味を持っても学び始める手段がない」という状態が続いています。
COBOLは「難しいから」敬遠されているのではなく、単に“見えない場所”に追いやられ、誰にも気づかれていないというのが実情です。
学ばせたくても、教える人がいない
企業がCOBOL人材を内部で育てようと考えたとしても、現実的にはその手段が限られています。なぜなら、教える側となるベテラン技術者は、日々の運用業務に追われており、教育に時間を割く余裕がないからです。
加えて、COBOLに携わる現場の多くは、そもそも「人を育てる」前提で設計されていません。これまでの属人化された運用スタイルが、そのまま「教える文化の喪失」へとつながっています。
また、長年その技術に慣れ親しんできたがゆえに、「他人にどう説明すればよいかが分からない」という悩みも多く聞かれます。文書化がされておらず、暗黙知として保有している情報を言語化することに抵抗や難しさを感じているケースも少なくありません。
こうした現場では、技術ドキュメントの整備そのものが後回しにされ、結果的に「人には教えられない」「人を増やせない」体質を強めてしまっています。
さらに、若手人材との世代間ギャップも課題となります。50代・60代のベテラン技術者と20代・30代の若手社員とでは、前提知識も価値観も大きく異なります。「教える側が古すぎて話が通じない」「若手が全く興味を持てない」といったミスマッチが起きやすい構図の中、技術以外の部分でもコミュニケーション障害が生まれてしまいがちです。
こうしてCOBOL人材の育成は、「教える人がいない」「教える準備がない」「教える仕組みもない」という三重苦の中で、ますます難易度が高くなっているのです。
学習者ゼロ時代に求められる“継承の仕組み”
COBOL人材が自然に供給される時代が終わった今、企業は「自社で若手を育成する」ことを前提にするのではなく、むしろ「COBOLを扱える人材が存在し続ける体制をどう外部に確保するか」を戦略的に考える必要があります。
まず注目すべきは、COBOL技術者の教育を継続している“海外の供給源”です。たとえばベトナムやフィリピンなど、一部のアジア諸国では、依然としてCOBOLを含むレガシー技術の教育が大学や民間教育機関で行われています。これらの国々では、「COBOLがニッチであるがゆえに、差別化要素になる」として、あえてCOBOLスキルを持った人材を輩出し続けている教育文化があります。
さらに、実際にCOBOLに特化したチームを形成し、日本向けの保守業務に長年対応してきたオフショア開発会社も存在します。こうしたパートナーと協業し、国内では確保が難しい領域を安定的に外部委託する体制を構築する企業も増えています。
私たちも、まさにこうしたニーズに応えるため、COBOL専任チーム×日本人PMOの体制で、長期的な保守支援に取り組んでいます。 実務を深く理解し、属人化を防ぎながら継承を可能にする体制こそ、これからの“仕組み化”に必要な要素だと考えています。
当社サービスの実際の支援内容やチーム体制については、資料にてご紹介しています。
【資料ダウンロードはこちら】
もちろん、すべてを外部に任せるというのではなく、社内に“本質理解者”を残しつつ、外部の力を戦略的に組み合わせることで、「社内に人がいないからCOBOLは継承できない」という状態を回避することが可能になります。
継承とは「教えること」ではなく、「仕組みを維持すること」だという視点に立てば、人材ゼロでもCOBOLを使い続けられる道はまだあります。その一つが、オフショア活用や外注化を前提としたCOBOL保守体制の再設計なのです。
まとめ:属人化は“過去の構造”が引き起こした、今求められる継承モデル
いかがでしたか?
若手人材にCOBOLを教える——この言葉の裏には、「教える人がいる」「教える時間がある」「教える意味がある」という前提が含まれています。しかし、そのいずれもが崩れつつある今、私たちが向き合うべきなのは「COBOLをどう継がせるか」という視点です。
学ばれる環境が失われ、教える人もいない中で、COBOL資産を持つ企業が今できることは、“学ばせること”ではなく“継がせる体制”の確保です。社内人材だけでなく、外部パートナーや海外人材との連携も視野に入れ、「使い続けられる状態」をいかに維持するか——それがこの時代における、最も現実的で持続可能な戦略と言えるでしょう。