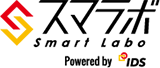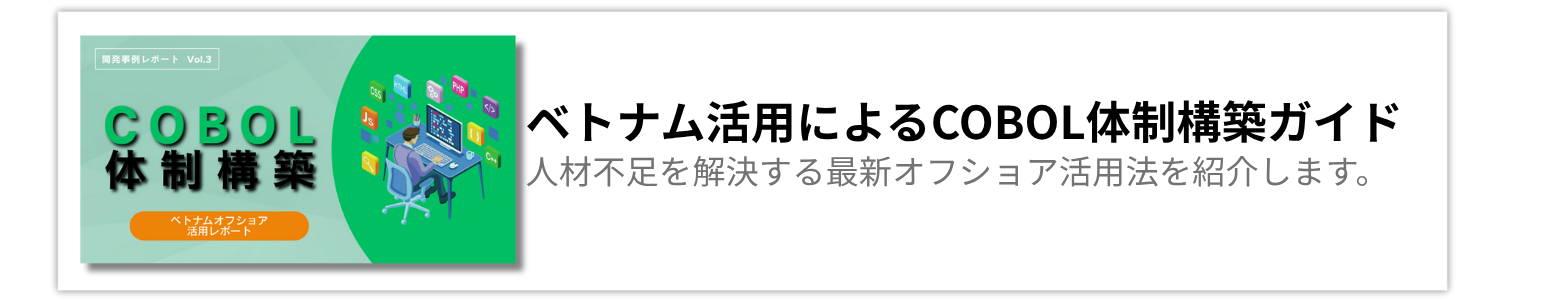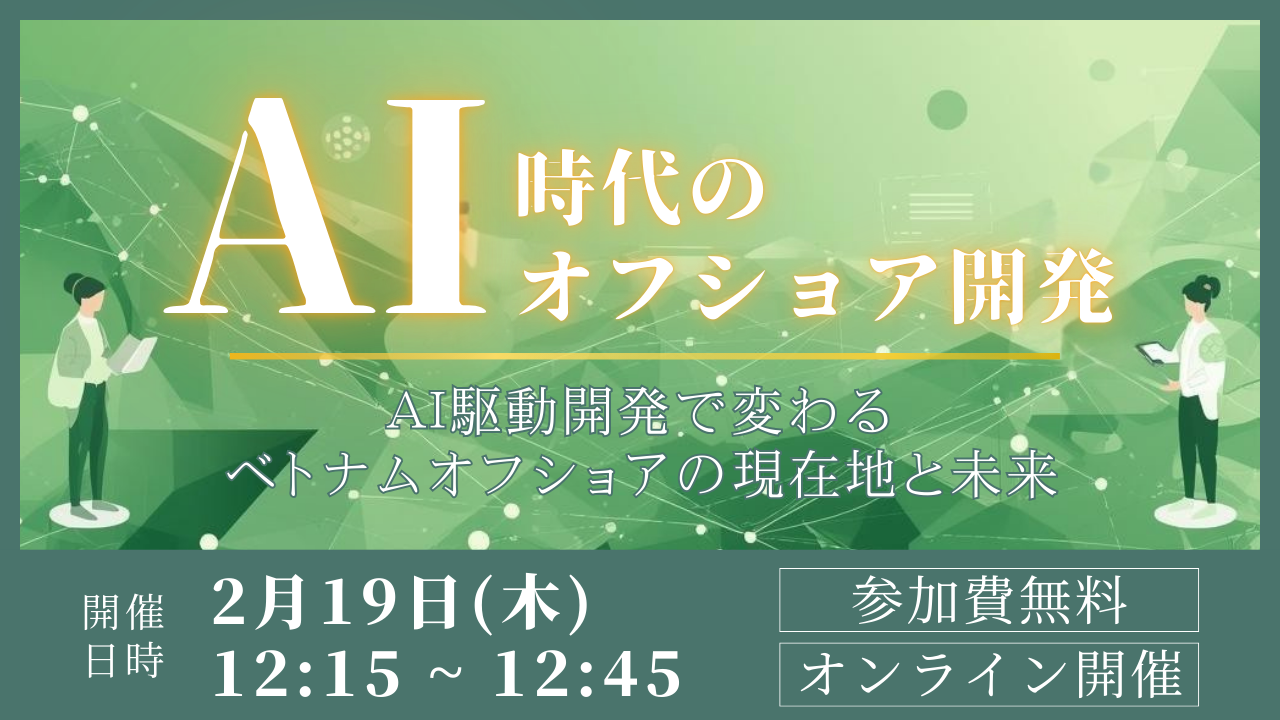こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
COBOL(コボル)という言語の名前を聞くと、多くの人は「古い」「時代遅れ」「もう使われていない」といったイメージを持つかもしれません。
実際、COBOLは1959年に誕生した非常に歴史のあるプログラミング言語であり、現代的なWebアプリやモバイルアプリの開発に用いられることはほとんどありません。
エンジニアコミュニティでも、COBOLを日常的に書いている人はごく一部。SNSで情報を見かけることも少なく、若手エンジニアの多くは触れる機会すらないでしょう。
では、COBOLはもう“終わった技術”なのでしょうか?
──答えは「NO」です。
COBOLは今も日本国内の多くの企業システムで現役で稼働しており、しかも止められない状況にあります。
実は、銀行、保険、製造、公共機関などの基幹システムにおいて、COBOLはなくてはならない存在なのです。
この記事では、なぜCOBOLが「古いのに消えないのか?」について、構造的な背景から5つの観点で整理し、今も現場で使われ続けている理由を紐解いていきます。
この記事はこんな人にオススメ!
- 自社のCOBOL資産が“なぜ残っているのか”をあらためて整理したい
- 「マイグレーションしなきゃ」と焦っているが、現実的に難しい事情がある
- レガシー問題を社内で説明・共有するための材料がほしい
目次
安定性・信頼性が高い

COBOLがここまで長く使われてきた最初の理由は、その圧倒的な安定性と信頼性です。
COBOLで構築されたシステムは、数十年にわたり一度も重大障害を起こすことなく稼働し続けているケースも多くあります。
特に、銀行の預金管理システム、公共の年金・税務システム、大手製造業の受発注・在庫システムなど、極めて高い信頼性が求められる領域ではCOBOLの堅牢さが評価されてきました。
COBOLはそもそも「ビジネス向け言語(COmmon Business-Oriented Language)」として設計されており、大量データ処理に向いた構造と、誤解しにくい記述スタイルを持っています。
そのため、長期運用に適した設計であり、稼働年数の長さ=信頼性の証明となっているのです。
基幹業務を支えるコアに組み込まれている
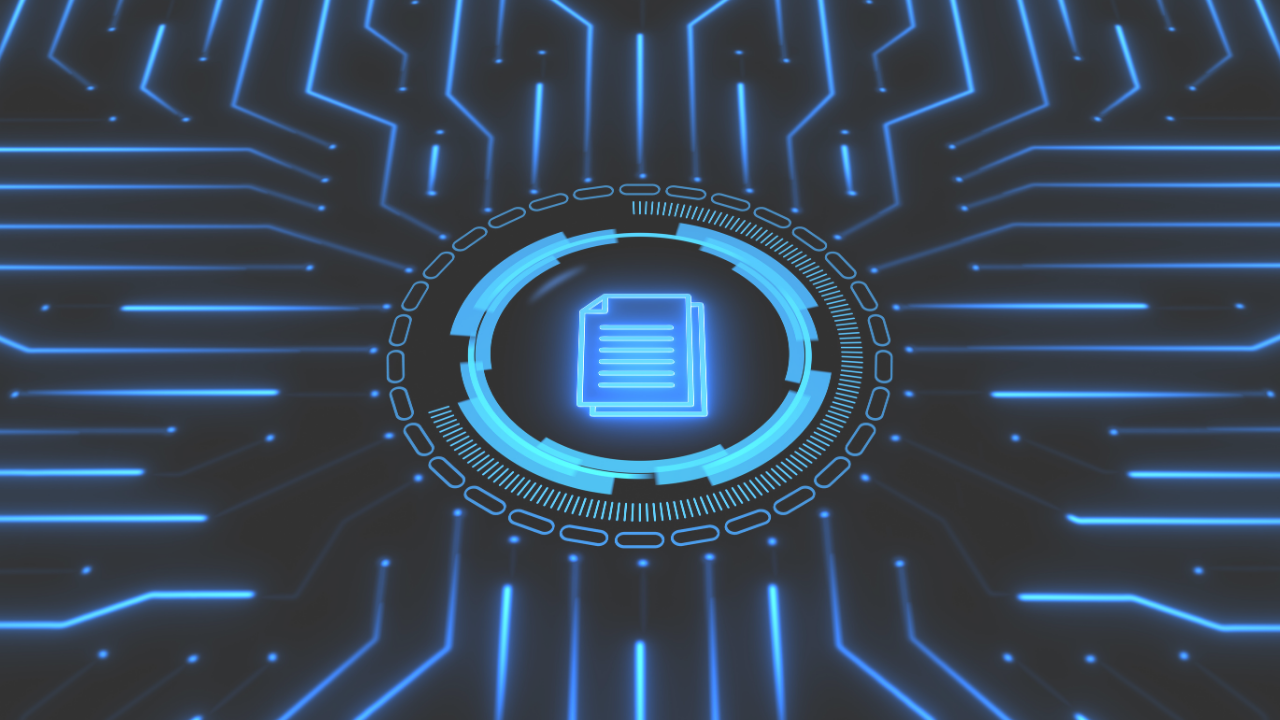
COBOLが“消せない”最大の理由のひとつは、システムの中心部に組み込まれているという構造的な事情です。
たとえば、大企業や公共団体の業務システムには、「勘定系」「受発注」「在庫管理」「給与」「請求」などの処理があり、これらの最重要処理がCOBOLで組まれているケースは珍しくありません。
このような基幹システムは、周辺のフロントエンドや帳票出力と密に連携しているため、COBOL部分だけを切り出して入れ替えるのが非常に難しいのです。
ある部分を変えようとすると、他の業務にも波及して想定外の不具合が出る──そんなジェンガのような構造の中に、COBOLは存在しています。
そのため、たとえ古くても、壊すわけにはいかない=だから使い続けるという判断がなされているのです。
移行コストとリスクが膨大すぎる

「じゃあCOBOLを最新の言語に書き換えればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、それは決して簡単な話ではありません。
理由は大きく2つ:
コストが莫大
COBOLで組まれたシステムは、業務処理の中核を担っている分、非常に大規模です。単純なコードの量だけでも数十万〜数百万行というケースがあり、全体を把握するだけでも膨大な時間と工数がかかります。
そのうえで、仕様を再定義し、テストを重ね、切替タイミングを慎重に見極めながらリリースする──この全プロセスには数年単位・数億円規模の投資が必要になります。
リスクが高い
過去には、無理なマイグレーション(移行)が原因で業務停止やトラブルが発生した事例も報告されています。
たとえば「移行先でバグが発生し、受注処理が止まった」「新システムに慣れず現場が混乱した」といった声は、実際に多くの現場で聞かれます。
こうしたコストとリスクを秤にかけたとき、企業がCOBOLを「まだ使えるから続けよう」と判断するのは、むしろ合理的な選択なのです。
ドキュメントも人材も“属人化”している

COBOLを刷新しづらい背景には、“人”の問題も深く関わっています。
長年にわたってCOBOLを扱ってきたベテラン社員が、その仕様・設計・背景を暗黙知として把握しているというケースが非常に多く、逆に言えば「その人がいないと何もわからない」状態に陥っている企業も珍しくありません。
さらに、設計書や仕様書が紙ベースで保管されていたり、更新されていなかったりして、実装とドキュメントが大きく乖離している場合もあります。
つまり、COBOL自体の問題ではなく、「COBOLとそれを支えてきた人」が一体化してしまっている構造が、企業の“身動きを取れなくしている”のです。
▼こちらの記事で、COBOL人材の高齢化問題についても詳しく解説しています▼
COBOL人材の高齢化問題、どう向き合う?企業が今やるべきこと
現在も“改修”や“追加対応”が求められている

驚かれるかもしれませんが、COBOLは単に“古いシステムをそのまま使っている”だけではありません。
実際には、制度改正や業務変更に応じて日々の改修や追加開発が行われているケースも多く存在します。
たとえば、税率改定、支給ルールの変更、新しい帳票フォーマット対応など、COBOLで動いている処理部分に修正を加える必要が出てくるたびに、担当者がソースを開いてメンテナンスしています。
つまり、COBOLは“放置された死蔵資産”ではなく、今も手を入れながら使われている“現役の戦力”だということです。
まとめ:COBOLは“古い”が“終わっていない”
いかがでしたか?
ここまで紹介してきたように、COBOLが消えない理由は、単なる技術選好や古いものへの執着ではありません。
- 安定性と信頼性が高く
- 基幹系の中心に組み込まれており
- 移行には莫大なコストとリスクがあり
- 属人化とドキュメント不在が障壁となり
- 今なおメンテナンスが必要な現場がある
──これらの要因が複雑に絡み合う中で、COBOLは“古いけれど終わらない技術”として、今も使われ続けているのです。
▼COBOL資産の維持をお考えの方へ。教育・継承を支えるオフショア保守体制をご紹介中!▼
次回予告(後編へ)
後編では、「ではこのCOBOLをどう扱うべきか?」という視点から、「刷新」か「維持」か、あるいはその中間か?——という現実的な選択肢を深掘りしていきます。
属人化を防ぎ、事業継続性を確保しながらCOBOL資産と共存するための手段として、オフショア保守や継承体制の構築についても詳しく紹介します。
「マイグレーション一択ではない」という視点をお探しの方は、ぜひ下のリンクから後編もご覧ください。