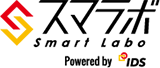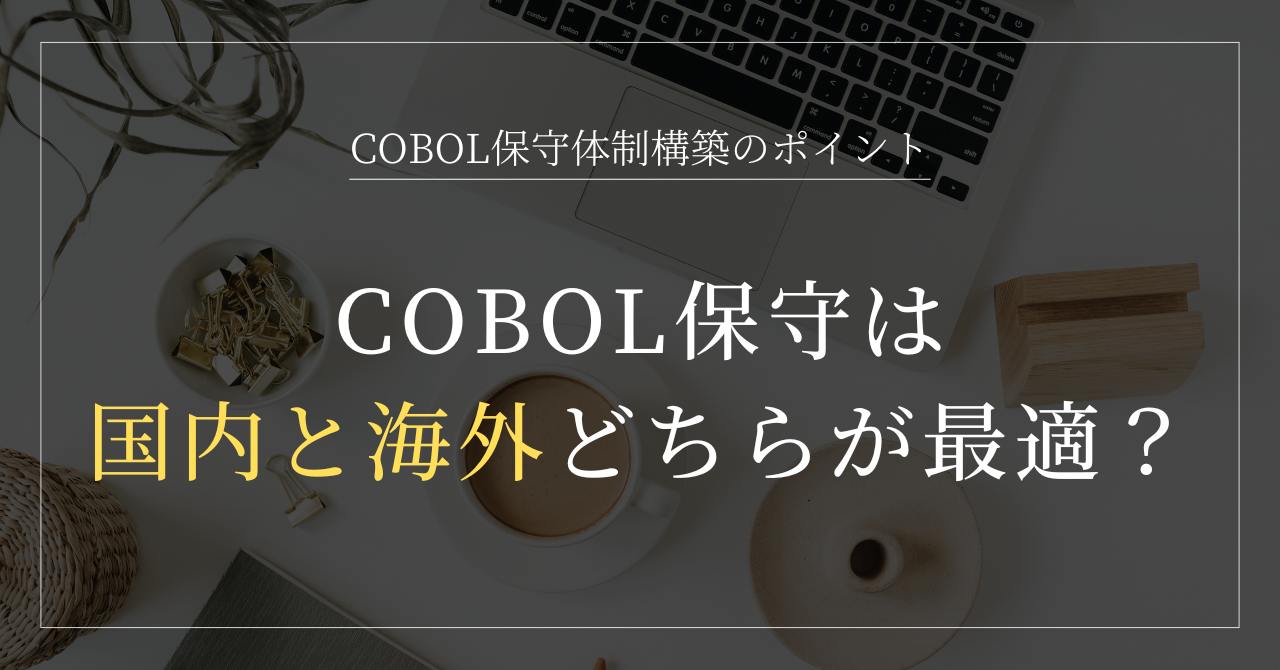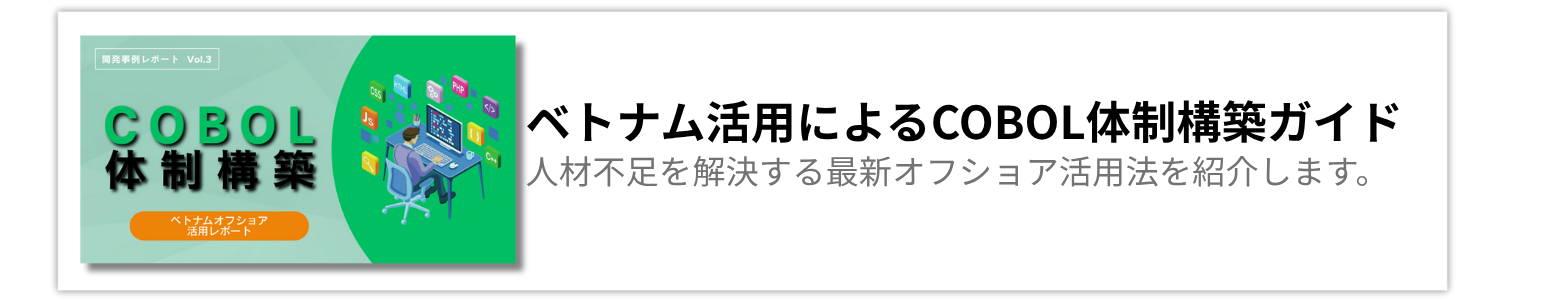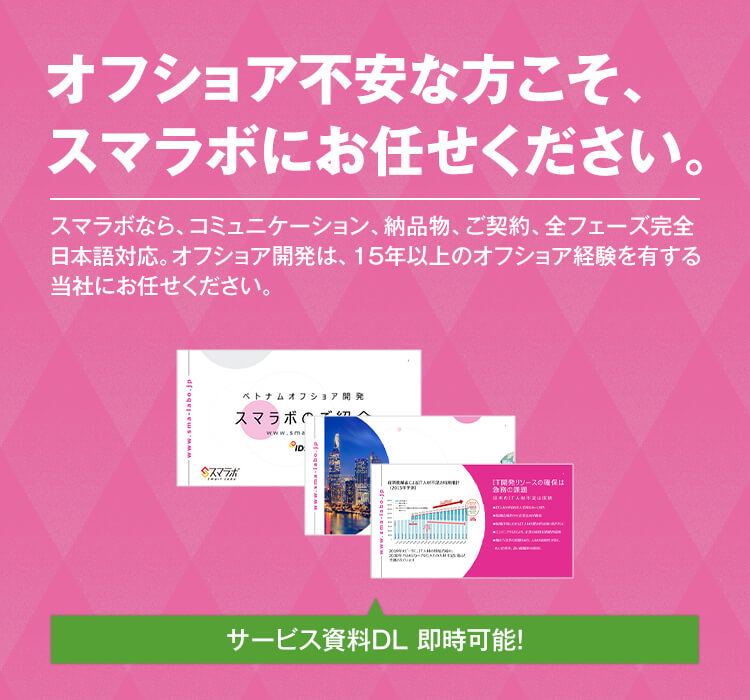こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。
国内のCOBOLエンジニアは年々減少し、高齢化も進んでいます。採用市場では経験者の確保が難しく、若手を育てても定着しないという課題を抱える企業が増えています。
一方で、COBOLシステムは基幹業務を支える重要資産であり、短期的なマイグレーションが難しいケースも多く、長期的な運用保守が必須です。
その結果、「どのような体制でCOBOL保守を維持すべきか」という問いに直面する企業が増えています。国内でチームを構築するか、海外オフショアを活用するか――どちらも一長一短があり、理想的なチーム像を描くことは簡単ではありません。
本記事では、国内委託と海外オフショアの違いを整理し、COBOL保守チームの理想形を探ります。
この記事はこんな人にオススメ!
- COBOL保守を国内委託で続けているが、人材確保に限界を感じている
- 長期的に安定したCOBOL保守体制を構築する方法を探している
- 海外オフショア活用を検討しているが、国内との違いが知りたい
▼COBOL人材の確保に限界を感じている方へ|長期安定のCOBOL保守体制を資料で解説しています▼
目次
COBOL保守チームに必要な要素とは

まず、どのような体制であってもCOBOL保守チームに求められる基本要素は共通しています。安定運用には、役割ごとの明確な分担が不可欠です。
中心となるのは、業務知識が豊富でシステム全体を俯瞰できるシニアエンジニアです。シニアが業務要件やコード資産を把握し、チーム全体をリードすることで品質が維持されます。次に、実際の改修やテストを担うミドル・ジュニアエンジニアが必要です。属人化を防ぐには、若手を適切に育成しながらチーム内でスキル移転を進める仕組みが求められます。
また、開発と並行して品質を管理するQC(品質管理担当)も欠かせません。長期運用では小さな改修の積み重ねが大きな障害につながるため、レビューやテストプロセスの徹底が重要です。さらに、国内外問わず、コミュニケーションを円滑にするコーディネーター役が体制の安定に大きく影響します。海外オフショアでは特にBrSE(ブリッジSE)の存在が重要で、国内チームでも部門間をつなぐ役割を担う人材が必要です。
理想のCOBOL保守チームは、こうした役割がバランスよく配置され、属人化しない運用プロセスが確立されていることが条件になります。
国内委託チームの特徴と限界

国内委託には、大きな強みがあります。最大のメリットは、業務理解の深さと即時対応力です。国内ベンダーは顧客企業の業務知識が豊富で、日本語での密なコミュニケーションが可能なため、急な仕様変更や法改正にも柔軟に対応できます。
しかし、課題も深刻です。コストが高く、長期体制を維持しにくい点が大きなネックです。経験豊富なエンジニアほど単価が高く、限られた予算で必要な人数を確保することは困難です。さらに、若手のCOBOL技術者は減少しており、長期的に同じメンバーでチームを維持するのは現実的ではありません。
国内委託は短期的な保守やスポット対応には向いていますが、10年先を見据えた長期体制の構築には限界があるといえます。
海外オフショアチームの特徴と最新事情

海外オフショアは、コスト面と人材確保の両面で国内委託を補う選択肢です。かつては中国オフショアが主流で、豊富な日本語人材と低コストが魅力でした。しかし、現在は状況が大きく変化しています。
中国では人件費が高騰し、コストメリットが縮小しています。さらに、若手エンジニアはモダンな開発言語を志向する傾向が強く、COBOL人材の確保が難しくなっています。セキュリティ面の懸念や地政学リスクもあり、多くの企業が中国オフショアからの撤退(いわゆるExit China)を進めています。
こうした中で、新たに注目されているのがベトナムです。ベトナムは豊富なIT人材供給を背景に、大学と連携してCOBOL人材を育成する仕組みが整いつつあります。特に地方拠点では地元志向が強く、長期定着が期待できる点が大きな魅力です。また、日本語教育や品質管理に日本式を取り入れる企業も増えており、以前より品質面への不安は低減しています。
▼以下の記事でオフショア開発における中国とベトナムの最新トレンドを解説しています▼
COBOL保守は中国からベトナムへ?Exit Chinaで変わるオフショア選び
理想のCOBOL保守チームはどう作るべきか
理想のCOBOL保守チームを作るうえで重要なのは、「短期的にしのぐか、長期的に維持するか」という軸で考えることです。
短期的に法改正対応などをこなすだけなら、業務理解の深い国内委託が適しています。一方、10年単位でCOBOL資産を維持するなら、海外オフショアの活用は現実的な選択肢です。特に、BrSEが常駐して国内側と連携し、大学連携で若手人材を育成できる体制は、長期的な安定を実現する鍵となります。
初期は5名程度の小規模体制から始め、徐々に拡大するステップ型構築が推奨されます。最初にシニアエンジニアが業務内容を整理し、BrSEがナレッジトランスファーを行うことで、属人化を防ぎながらスムーズに立ち上げが可能です。
こうした体制を提供するオフショア企業はまだ多くはありませんが、大学連携や日本式教育を取り入れる企業も現れ始めています。これらを選ぶことが、理想のCOBOL保守チーム構築の近道になるでしょう。
▼ COBOL人材の確保に限界を感じている方へ |長期安定のCOBOL保守体制を資料で解説しています▼
まとめ: 自社に合う体制を選ぶために考えるべきこと
いかがでしたでしょうか?
COBOL保守チームに「絶対的な正解」はありません。重要なのは、自社のシステムが「短期的な延命」なのか「長期的な維持」なのかを見極め、それに合った体制を選ぶことです。
国内委託だけに頼る時代は終わりつつあり、長期体制を構築するなら海外オフショア活用が現実的です。特に、大学連携やナレッジトランスファーを仕組み化できる体制は、長期的な安定を求める企業にとって有力な選択肢となるでしょう。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!